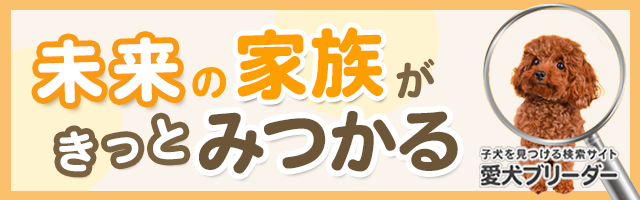犬が「クンクン」と鳴くのはなぜ?甘え・不安・病気の可能性や対処法を解説
公開日:2025年4月7日
更新日:2025年5月28日

犬の「クンクン」という鳴き声は、飼い主にとって愛犬の気持ちを知る手がかりの一つです。
犬は無言のコミュニケーションを持つ生き物であり、この鳴き声には特定の意味が隠されています。
愛犬が何を思って鳴いているのか、なぜ鳴いているのか、行動を見守ることでその真意に迫ることができるでしょう。
[目次]
犬が「クンクン」鳴く理由
犬が「クンクン」と鳴く理由はさまざまで、主に飼い主へ何かを伝えたいときにみられる行動です。甘えたい気持ちや何かをおねだりしたいという欲求、あるいは不安や恐怖を感じているサインかもしれません。
考えられる理由をいくつか紹介しますので、愛犬が伝えたいことは何かをひも解く際の参考にしてみてください。
クンクン鳴く理由①甘えたい、かまってほしい
「寂しい」「こっちを向いてほしい」という感情からくる行動と考えられ、飼い主への信頼や愛情表現のひとつといえます。
こうしたサインを見逃さず、飼い主としても愛犬に寄り添って過ごす時間を増やすとよいでしょう。
ふれあいの時間をもつことで、愛犬はより安心感を得ることができ、一層絆が深まります。
遊んであげたり、撫でてあげたりすることで相互の信頼感が高まり、より良い関係が築けるはずです。
クンクン鳴く理由②何かおねだりしたいことがある
食べ物をおねだりするときにも「クンクン」と鳴くことがあります。
例えば、おやつや食事の準備中にこのような鳴き声を発する犬は、食べ物の匂いに反応しながら「もっとほしい」「早くちょうだい」と要求していることが多いです。
この場合、愛犬の健康や適切な食事量を考えつつ、落ち着いて対応することが重要です。
クンクン鳴く理由③不安なことや怖いことがある
犬は、不安や恐怖を抱えているときも「クンクン」と鳴く傾向があります。
例えば、一人にされて寂しいと感じたときや、大きな音に驚いたときなど、環境や状況が原因となる場合が多いです。
「助けてほしい」「守ってほしい」という気持ちが込められていることもあるため、不安を取り除いてあげられることがあるか愛犬をよく観察しましょう。
クンクン鳴く理由④ストレスを感じている
犬がストレスを感じている時にも「クンクン」と鳴くことがあります。不安や緊張、不満といったネガティブな感情の表れとして現れることが多いです。環境の変化や運動不足、飼い主とのコミュニケーション不足などが原因となる場合があります。愛犬が何にストレスを感じているのか、原因を探って取り除いてあげることが大切です。
クンクン鳴く理由⑤痛みや体調不良がある
犬がクンクンと鳴く場合、体のどこかが痛い場合や不調を抱えている可能性も考えられます。特に、鳴き声に加えて震えている、背中を丸めている、触ると嫌がるなどの様子が見られる場合は、痛みを訴えているサインかもしれません。普段と違う様子が見られたら、早めに動物病院を受診しましょう。
犬が「クンクン」鳴くときの対処法
犬がクンクン鳴く行動は、その理由によって適切な対処法が異なります。
甘えや要求、不安やストレス、あるいは病気の可能性など、愛犬がなぜ鳴いているのかを理解することが第一歩です。
それぞれの状況に合わせた対処法をいくつかご紹介します。
甘えや要求への対処
甘えや要求からクンクンと鳴いている場合には、毎回応じるのではなく犬が落ち着いたタイミングでかまうようにしましょう。興奮している時に相手をすると「鳴けば要求が通る」と学習し、わがままな性格になってしまう可能性があります。
また、遊びや要求に応じる時間には終わりがあることを教えるのも大切です。
遊びを切り上げる際に「おしまい」などの合図を決め、それを理解させることで、犬は要求が通らない場面も受け入れやすくなります。
不安やストレスへの対処
犬が不安やストレスを感じて「クンクン」鳴いている場合は、環境の変化や見慣れないもの、大きな音などに驚いたり、一人にされて寂しさを感じたりすることが原因となることが多いです。
そうした不安やストレスを和らげるためには、安心できる場所を提供したり、規則正しい生活を送らせたりすることが大切です。
また、適度な運動やノーズワークなどで気分転換を図ることも効果的です。
病気の可能性も考えよう
犬が「クンクン」と鳴く場合、単なる要求や甘えではなく、病気が隠れている可能性も考慮する必要があります。
普段と違う鳴き方をしている、ぐったりしている、食欲がないなど、鳴き声以外の症状が見られる場合は注意が必要です。痛みや体調不良を「クンクン」という鳴き声で訴えている場合も少なくありません。
また、高齢の犬が頻繁に「クンクン」鳴くようになった場合は、認知症の可能性も考えられます。 様子がおかしいと感じたら、早めに動物病院で診察を受けることが大切です。病気の早期発見・早期治療に繋がる可能性があります。
犬が「クンクン」鳴くのは子犬の頃の名残?
犬の「クンクン」という鳴き声は、子犬の頃に培われた行動の一つであり、重要なコミュニケーション手段です。
母犬に対して自分の居場所を知らせたり食事を要求したりすることが一般的で、母親代わりとなった飼い主に甘えたい時や何かを要求している時に、子犬の頃の名残としてこの鳴き声を使うことがあります。
この「クンクン」という鳴き声は、成犬になった後も多くの犬にとって残り続ける行動です。
要求の応えすぎに注意しながらも、「愛情」や「安心」「信頼」などは声や態度でしっかり伝わるよう工夫しましょう。
犬が「クンクン」鳴くのに性格は関係ある?
よく「クンクン」と鳴く犬は、甘え上手な一面や寂しがり屋な性格をもつ傾向がみられます。
飼い主に対して甘えたいという気持ちが強い場合、愛情を求めたり、飼い主の注意を引きたいという感情がその背景にあることが多いです。
一方、寡黙な性格の犬は「クンクン」と鳴くことが少ない場合がありますが、この違いは性格としての特徴だけでなく、犬が置かれている状況や環境にも影響されます。
「クンクン」と鳴く頻度やタイミング、仕草などを観察することで、愛犬の性格や一時的な感情を読み取る手がかりとなるでしょう。
老犬がクンクン鳴くのはなぜ?
老犬がクンクン鳴くのにはいくつかの理由が考えられます。
要求や甘えからくる場合もありますが、加齢に伴い、関節炎やその他の病気が原因で痛みが生じ、それが鳴き声につながる場合もあります。
特に夜間に頻繁に鳴く場合は、認知症の可能性も考えられます。鳴き声だけでなく、行動や仕草も観察し、愛犬の状態をよく把握することが大切です。
老犬の要求鳴きへの対処法
老犬の要求鳴きには、まず何を求めているのかを観察し、可能な範囲で応えてあげることが大切です。
食事の時間調整や、排泄のタイミングを考慮するなど、愛犬の生活リズムに合わせたケアをすることで要求鳴きが減る場合があります。
トイレに行きたくて鳴いている場合もあるため、何を望んでいるのか理解する必要があります。
夜間の鳴きが多い場合は、寝床の環境を見直したり、安心できる空間を整えたりすることも有効です。
老犬が不安や寂しさを感じて鳴いている場合
老犬が不安や寂しさからクンクン鳴く場合、そばに寄り添って安心させてあげることが大切です。優しく撫でてあげることで、不安な気持ちが和らぎ、落ち着くことがあります。
老犬になると視覚や聴覚が衰え、周囲の状況を把握しづらくなることで不安を感じやすくなるため、飼い主さんの存在を感じられるように配慮してあげましょう。
夜間に鳴く場合は、寝床を飼い主さんの近くに移動させるのも効果的な場合があります。
老犬が体の痛みから鳴いている場合
老犬がクンクンと鳴く場合、体のどこかに痛みを感じて鳴いている可能性も考えられます。
クンクン鳴く以外に、特定の場所を触られるのを嫌がる、動きが鈍くなった、といった症状が見られる場合は注意が必要です。
これらの症状が見られる場合は、病気が原因である可能性が高いため、早めに動物病院で診察を受けることをおすすめします。
まとめ|犬がクンクン鳴いているときは状況に応じた対処が必要
犬が「クンクン」と鳴くのは、甘えたい時や何かをおねだりしたい時、不安や恐怖を感じた時など、さまざまな心情を表現しています。
愛犬が鳴く理由を理解し、その背後にある気持ちを敏感にキャッチすることが大切です。
性格や状況に応じた適切な反応をすることで、より強い信頼関係を築き、絆を深めることができるでしょう。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、少額短期保険募集人の資格を保有。
豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら
犬との暮らしの関連記事
犬との暮らしの記事一覧を見る人気の記事
新着記事