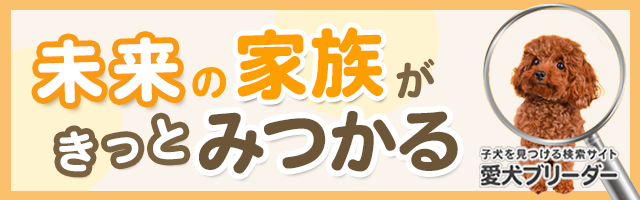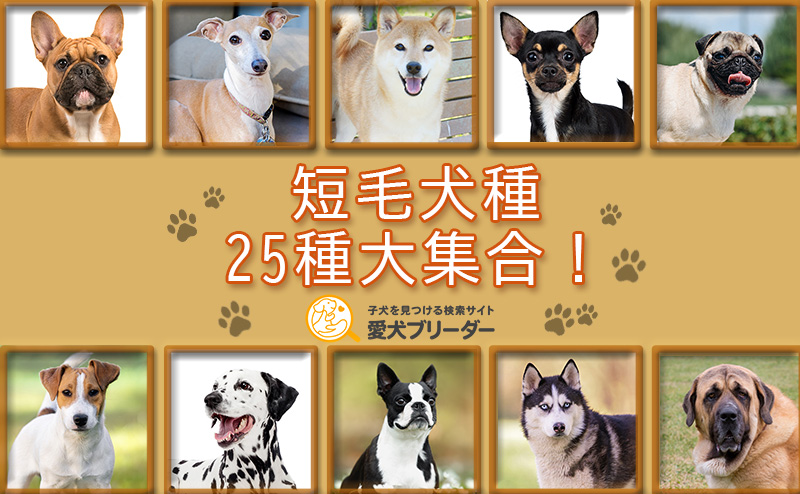犬の分離不安症の治し方は?初期症状や重症化の原因、なりやすい犬種も!
公開日:2025年9月24日
更新日:2025年9月24日

飼い主の留守中などに、愛犬が問題行動を起こすことに頭を悩ませていませんか?犬の「分離不安症」は、吠え続ける・粗相・家具破壊などの行動としてあらわれます。
本記事では、犬の分離不安症について、具体的な症状や原因、改善のための対策まで詳しく解説します。分離不安になりやすい犬種ランキングも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
[目次]
犬の分離不安症とは何か?
犬の分離不安症とは、飼い主や家族など愛着のある存在と離れることに、強い不安や恐怖を抱く精神的な問題です。留守番中に吠え続ける、家具を破壊する、粗相をするなど、普段はみられない行動があらわれるのが特徴です。
犬の分離不安症の症状は、初期の「粗相」「落ち着きのなさ」から、進行すると「自傷行為」や「ノイローゼ状態」に至ることもあります。重要なのは、これらの行動がわざとや反抗によるものではなく、犬自身がコントロールできない強いストレスによる反応だという点です。
分離不安症は一時的な甘え癖とは異なります。行動学的な治療・トレーニング、場合によっては薬やサプリなどによるサポートが必要な問題です。犬の気持ちを理解し、早期に適切な対処を行うことが愛犬と飼い主双方の安心につながるでしょう。
犬の分離不安症チェックリスト│見分ける10個のサイン

愛犬の行動が分離不安症によるものかを見極めるため、具体的なサインをチェックリストとして紹介します。ただし、これはあくまで簡易的なセルフチェックであり、最終的な診断は動物病院の獣医師に相談しましょう。
- ①初期症状:物を壊す
- ②初期症状:粗相が増える
- ③初期症状:吠え続ける
- ④初期症状:常に飼い主から離れない
- ⑤初期症状:夜泣きが続く
- ⑥重症:過剰によだれを垂らす
- ⑦重症:帰宅時におしっこを漏らす
- ⑧重症:自分の手足を噛む・舐める
- ⑨重症:体の震えがとまらない
- ⑩重症:下痢や嘔吐をする
①初期症状:物を壊す
飼い主がいない間に、家具やクッション、スリッパなどを破壊する行動は、分離不安症の代表的な症状の一つです。特に、飼い主の匂いが強く残っているものをターゲットにすることが多く、これは不安を紛らわそうとするための行動と考えられます。
単なるいたずらとは異なり、ドアや窓の周りを執拗に引っ掻いたり、噛んだりする行動がみられる場合、飼い主を探して外に出ようとパニックになっている可能性があります。
②初期症状:粗相が増える
飼い主が留守番中に限って、トイレ以外の場所で排泄してしまうのも、分離不安症が疑われるサインです。これは、強い不安やストレスによって排泄をコントロールできなくなる生理的な反応、いわゆるお漏らしに近い状態です。
特に飼い主のベッドの上やソファなど、匂いが強く残る場所で粗相をすることが少なくありません。帰宅後にこれを発見しても、犬を叱ることはせず、不安の原因を取り除くことに目を向けてあげましょう。
③初期症状:吠え続ける
飼い主が出かけてから帰宅するまで、遠吠えや甲高い声で鳴き続ける行動も、分離不安症の典型的な症状です。この鳴き声は、来客や物音に反応して警戒する際の吠える行為とは異なり、飼い主を呼び戻そうとする悲痛な叫びであることが特徴です。
飼い主の不在に対する不安や寂しさから吠え続けるため、長時間にわたることが多く、近隣トラブルに発展するケースも少なくありません。留守番中の様子を室内カメラなどで確認してみると、こうした行動に気づくことがあります。
④初期症状:常に飼い主から離れない
飼い主が在宅している時でも、ストーカーのようについて回り、トイレや浴室にまで入ろうとする行動も分離不安症の兆候です。これは「後追い」と呼ばれ、飼い主の姿が見えなくなるだけで強い不安を感じるために起こります。
常に飼い主の体に触れていないと落ち着かず、少しでも距離ができると鳴いたりソワソワしたりする様子がみられます。このような過度な依存は、犬が精神的に自立できていない状態を示しており、飼い主との間に適切な距離感を築けていないサインと捉えることができます。
⑤初期症状:夜泣きが続く
飼い主と寝室が別であったり、ケージやサークル内で寝かせたりしている場合に、夜間に不安から鳴き続ける「夜泣き」も分離不安の症状として現れることがあります。
子犬が新しい環境に慣れずに鳴くのとは区別が必要で、成犬になってもこの行動が改善されない場合は分離不安が原因かもしれません。昼間の留守番だけでなく、夜間も犬が安心できない状態にあることを示唆しています。
⑥重症:過剰によだれを垂らす
極度の不安やストレスは自律神経の乱れを引き起こし、「よだれ」が過剰に分泌されることがあります。留守番をさせた後に、犬がいた場所の床やベッドがよだれでびしょ濡れになっている場合、分離不安が重症化している可能性があります。
これは、食事を前にした時やリラックスしている時のよだれとは明らかに量が異なり、口の周りが泡立っていることもあります。犬が相当な精神的苦痛を感じているサインであり、震えや呼吸が速くなるパンティングといったほかの症状を伴うことも少なくありません。
⑦重症:帰宅時におしっこを漏らす
飼い主が帰宅した際に、過度に興奮して「失禁」してしまうことがあります。これは子犬によくみられる、嬉しさのあまりおしっこを漏らしてしまう「嬉ション」とは少し異なります。
分離不安症の場合、長い不安から解放された安堵感と再会できた興奮が入り混じり、感情のコントロールが効かずに失禁に至ります。成犬になってもこの行動が続く場合は、留守番中に感じていたストレスが非常に大きかったことの表れかもしれません。
関連記事:犬はなぜ「うれしょん」するの?理由と正しい接し方・改善方法を解説!
⑧重症:自分の手足を噛む・舐める
飼い主の不在による強いストレスや不安を解消しようとして、自分の手足や尻尾の同じ箇所を執拗に舐めたり噛んだりする行動がみられることがあります。これは「常同行動」の一種で、精神的な葛藤を自分自身に向けて発散しようとする行為です。
この行動がエスカレートすると、その部分の皮膚が炎症を起こして赤くなったり、毛が抜け落ちたりする「舐性皮膚炎(しせいひふえん)」を引き起こします。とくに留守中に起こりやすいため、早めに気づき、自傷行為に発展する前に適切な対応をしてあげることが大切です。
⑨重症:体の震えがとまらない
飼い主の外出を察知した途端に、体が小刻みに「震える」のも重症化のサインの一つです。この震えは寒さや体調不良によるものではなく、これから一人にされることへの強い不安や恐怖からくる精神的な反応です。
震えと同時に、落ち着きなくウロウロと歩き回ったり、ハァハァと浅く速い呼吸(パンティング)をしたりといった行動がみられることもあります。留守番そのものが犬にとって耐え難い苦痛になっていることのあらわれです。
⑩重症:下痢や嘔吐をする
強い精神的ストレスは、消化器系の働きに影響を及ぼし、「下痢や嘔吐」といった身体的な症状としてあらわれることがあります。
特に、飼い主が留守にしている間に限ってこれらの症状が繰り返しみられる場合、分離不安症の可能性を考えなくてはなりません。ただし、これらの症状はほかの病気の可能性も十分に考えられるため、自己判断は禁物です。まずは動物病院を受診しましょう。
なぜ分離不安症に?考えられる5つの原因

犬が分離不安症になる原因は一つではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って発症します。ここでは、考えられる主な原因をいくつか見ていきます。
原因1:遺伝・犬種・性格の影響
犬の分離不安症は、生まれつき不安を感じやすい、怖がりといった遺伝的な要素や犬種特有の気質なども影響していると考えられています。
特に、愛玩犬種は、愛情を受けることを前提に改良されてきたため、飼い主への依存度が高くなりやすいでしょう。性格的には、甘えん坊で寂しがり屋、臆病なタイプの犬が発症しやすいとされます。
原因2:環境や生活リズムの変化
犬の分離不安は、以下のような環境の変化によるストレスが原因で生じることもあります。
- 引っ越しによる住環境の変化
- 飼い主の転職や家族の進学
- 留守番の時間が急に長くなる
- 出産や死別など家族構成の変化
これまで常に誰かが家にいた環境から、急に一匹で長時間過ごすことになると、犬は強い戸惑いと孤独を感じてしまうのです。
原因3:幼少期の社会化不足
子犬期に十分な経験をしていないことも、分離不安症の原因となりえます。生後3週〜14週前後の社会化期に大きな音、にぎやかな場所や乗り物、人やほかの犬との関わり、環境の変化などの多様な刺激に触れないまま育つと、臆病で不安を抱きやすい性格になりやすいでしょう。
結果として、飼い主に過度に依存してしまい、離れるだけでパニックを起こしやすくなるため、社会化は将来の分離不安予防に欠かせない基盤といえます。
原因4:飼い主との関係性や飼い方
飼い主の過保護な接し方や常に一緒に行動する生活は、犬の自立心を奪い分離不安を招きます。このような関係性では、犬は飼い主なしでは何もできないと学習し、飼い主への依存を強めてしまいます。
また、外出前や帰宅時に「ごめんね」「良い子にしてたね」などと大げさに声をかけたり、過剰に撫でたりすることも、留守番を特別なことだと犬に認識させ、かえって不安を煽る結果となります。犬との間に信頼に基づいた適度な距離感を保つことが大切です。
原因5:過去のトラウマ
犬が捨てられた経験や迷子、ネグレクトなどの過去のトラウマをもつ場合、「また見捨てられるのでは」という不安から、分離不安が強まることがあります。
特に保護犬の場合、見捨てられることへの強い恐怖心を抱えていることが少なくありません。このようなトラウマを抱えた犬は、新しい飼い主との間に強い絆ができた後、その飼い主と離れることに対して極度の不安を感じ、分離不安症を発症しやすくなります。
原因6:老化による認知機能の低下
老犬は認知症や視覚・聴覚の衰えにより状況判断が難しくなり、強い不安から分離不安症を発症することがあります。いわゆる犬の認知症です。
認知機能が低下すると、自分がどこにいるのか、今がいつなのかを把握するのが難しくなります。その結果、今まで平気だった留守番ができなくなり、飼い主の姿が見えないと鳴き続けるといった行動がみられるようになります。
ただし、老犬の場合、てんかんなどの病気が不安行動につながることもあるため、注意が必要です。
分離不安症になりやすい犬種ランキングTOP10
分離不安症は、歴史的背景や気質から、比較的になりやすいとされる犬種が存在します。ここでは、一般的に分離不安症になりやすい犬種を紹介しますが、あくまで傾向であり、個々の性格や育った環境が最も大きな要因であることを念頭に置いてください。
- 【第1位】トイプードル
- 【第2位】ポメラニアン
- 【第3位】ヨークシャーテリア
- 【第4位】ミニチュアダックスフンド
- 【第5位】マルチーズ
- 【第6位】キャバリアキングチャールズスパニエル
- 【第7位】シーズー
- 【第8位】ゴールデンレトリーバー
- 【第9位】ビションフリーゼ
- 【第10位】パグ
【第1位】トイプードル

トイプードルは非常に賢く、飼い主の感情を敏感に読み取る能力に長けています。そのため、飼い主との絆が深くなりやすい一方で、飼い主の不在を過剰に不安に感じてしまう傾向があります。
人と一緒に作業をしたり、喜ばせたりすることが大好きな性格です。この性質が、飼い主への強い依存心につながり、一人でいる状況に耐えられなくなることがあります。
【第2位】ポメラニアン

ポメラニアンは活発で好奇心旺盛、飼い主に対して非常に愛情深い犬種です。常に飼い主の注意を引き、一緒にいることを望む傾向が強く、その愛着の深さが分離不安につながることがあります。
体が小さく愛らしい見た目から、つい甘やかしてしまいがちですが、過保護な飼育は自立心を損なわせ、飼い主への過度な依存を助長する可能性があります。飼い主の姿が見えなくなるだけで吠え続ける、などの問題行動に発展しやすいとされています。
【第3位】ヨークシャーテリア

「動く宝石」とも呼ばれるヨークシャーテリアは、狩猟犬として活躍していた歴史をもちますが、飼い主に対しては非常に甘えん坊で、深い愛情を示します。
この独占欲の強さが、飼い主が自分から離れていくことへの強い不安や嫉妬心につながることがあります。常に飼い主のそばにいることを望み、一人にされると寂しさからストレスを溜め込みやすい性質を持っているため、注意が必要です。
【第4位】ミニチュアダックスフンド

ミニチュアダックスフンドは、自立心があり頑固な一面もありますが、その一方で非常に甘えん坊で、飼い主と一緒に遊んだりくっついたりすることが大好きです。このギャップが、飼い主への強い執着心を生むことがあります。
飼い主が外出するのを察知すると、後を追いかけたり、不安そうな素振りを見せたりすることが多く、留守番中にストレスから吠え続けたり、物を破壊したりする行動に出やすい犬種の一つとして知られています。
【第5位】マルチーズ

マルチーズは、古代から愛玩犬として飼育されてきた歴史を持つ、「抱き犬」の代名詞ともいえる犬種です。人懐っこく穏やかな性格で、飼い主に抱かれたりそばにいたりすることに最高の幸せを感じます。
そのため、一人で過ごすことが非常に苦手で、飼い主と離れると強い孤独感や不安に襲われやすい傾向があります。常に誰かと一緒にいることが当たり前の環境で育つと、留守番という状況に適応するのが難しくなり、分離不安の症状があらわれやすくなります。
【第6位】キャバリアキングチャールズスパニエル

キャバリアは、その名のとおり、王族の膝の上で過ごしてきた歴史があり、人と一緒にいることを何よりも好みます。攻撃性が低く、愛情深い性質は素晴らしい長所ですが、その反面、寂しがり屋で依存心が強くなりやすいでしょう。
飼い主と離れることに極度のストレスを感じ、留守番中にいたずらなど問題行動を起こすことが少なくありません。
【第7位】シーズー

シーズーは、家族と一緒に過ごす時間を好む一方で、プライドが高く頑固な一面もあり、自分の要求が通らないとストレスを感じることもあります。
飼い主への愛情が深い分、一人にされることへの寂しさも強く感じやすいです。甘やかしすぎると、飼い主への依存度が必要以上に高まり、留守番が苦手になってしまう傾向がみられます。
【第8位】ゴールデンレトリーバー

大型犬であるゴールデンレトリーバーは、非常にフレンドリーな性格で、飼い主を喜ばせたいという気持ちが非常に強い犬種です。この献身的な性質が、飼い主への強い依存心につながることがあります。
家族との絆が非常に深く、群れの一員であるという意識が強いため、一人で長時間取り残されると、強い孤独感や不安を感じて問題行動を起こすことがあります。十分な運動とコミュニケーションが必要です。
【第9位】ビションフリーゼ

ビションフリーゼは、明るく陽気で、人を楽しませることが得意で、常に注目の中心にいたいタイプです。この社交的な性格がゆえに、一人でいることが非常に苦手で、寂しさを感じやすい傾向があります。
飼い主と離れると、その存在を確かめるために吠え続けたり、気を引くための破壊行動に出たりすることがあります。常に人と一緒にいたいという欲求が強く、分離不安になりやすい犬種の一つです。
【第10位】パグ

パグは、飼い主に対して非常に愛情深い一方で、嫉妬深く頑固な一面もあり、飼い主の愛情を独占したいという気持ちが強いです。
飼い主が自分以外のものに注意を向けたり、外出したりすることに対して、強いストレスを感じることがあります。この愛情深さと独占欲の強さが、分離不安の引き金となりやすいと考えられています。
※こちらのランキングは、当社が独自に調査・作成したものです。あくまで目安としてご覧ください。
【おまけ】分離不安症になりにくい犬種は?
分離不安症になりやすい犬種と対比して、比較的自立心が高く留守番が得意な「分離不安症になりにくい犬種」も存在します。
- 柴犬
- ウェルシュコーギーペンブローク
- ボクサー
- シベリアン
柴犬などの日本犬は、精神的に自立している個体が多い傾向にあります。また、シベリアンハスキーやウェルシュコーギーペンブローク、ボクサーといった作業犬としての歴史を持つ犬種も、自分で考えて判断したり行動したりする能力が高く、留守番が得意なことも多いでしょう。
ただし、これはあくまで一般的な傾向です。また、個体差・育て方・過去の経験・老化によって分離不安症を発症する可能性は残るため、「なりにくい=絶対にならない」ではない点に注意してください。
犬の分離不安症の治し方│改善方法とNG対応
犬の分離不安症は、飼い主の接し方や生活環境を見直すことで、症状の改善や予防が期待できます。ここでは、日常生活で実践できる具体的な治し方やトレーニング方法を紹介します。
効果的な留守番トレーニングは?
分離不安の改善には、犬が一人でいることに少しずつ慣れさせるトレーニングが有効です。
まず、飼い主が家の中にいる状態から、別の部屋に行き数秒で戻ることから始めます。犬が落ち着いて待てたら褒め、少しずつ時間を延ばしたり、実際に玄関から出てみたりします。
外出時や帰宅時は、過剰に声をかけたりせず、冷静に振る舞うことが「お留守番は特別なことではない」と犬に教える上で重要です。
また、留守番中には、中にフードを詰められる知育トイなど、犬が集中して楽しめるアイテムを用意し、一人で過ごす時間にポジティブな印象を持たせることも効果的です。軽度の症状であれば、こうした地道なトレーニングで改善が見込めます。
犬に薬にサプリを与えても良い?
分離不安症の治療には、獣医師の診断のもとで、精神状態を安定させるための薬やサプリメントが用いられることがあります。これらは、犬の不安を和らげ、行動療法(トレーニング)を受け入れやすくする目的で使用されます。
しかし、飼い主の自己判断で市販のものを与えるのは絶対に避けてください。かならず動物病院で犬の状態に合った薬を処方してもらいましょう。薬物療法は、あくまでトレーニングと並行して行う補助的な手段であり、薬だけで問題が解決するわけではないことを理解しておく必要があります。
犬と一緒に寝るのは続けて良い?
犬と一緒に寝ることが分離不安症の直接的な原因になるわけではありませんが、症状がみられる場合には、犬の自立心を育てるために寝床を分けることを検討してみましょう。
一日中飼い主と密着している生活は、犬の依存心を強め、一人になることへの不安を増大させる可能性があります。
まずは同じ寝室内に犬専用のベッドやクレートを置き、そこで安心して眠れるようにトレーニングを始めるのが良いでしょう。急に突き放すのではなく、犬が安心できる快適な寝床を用意し、少しずつ一人で寝ることに慣らしていくステップを踏むことが大切です。
犬が吠え続けるのは無視するべき?
分離不安からくる吠えは、犬が不安や恐怖を感じていることの表現であり、完全に無視することは根本的な解決にはなりません。ただ、吠えるたびに飼い主が反応してしまうと、「吠えれば構ってもらえる」と学習し、要求吠えとして定着してしまうおそれもあります。
最も重要なのは、吠える原因である「一人でいることへの不安」そのものを取り除くことです。留守番トレーニングなどを通じて、犬が安心して過ごせる時間を増やしていくことが本質的な対策となります。吠えている最中に叱りつけるのは避けましょう。
犬を構いすぎると分離不安は悪化する?
犬を構いすぎるような過度な関わり方は、分離不安を悪化させる一因となり得ます。遊びや散歩の時間はたっぷりと愛情を注ぎ、それ以外の時間は犬が一人でリラックスして過ごす時間も作るなど、生活にメリハリをつけることが重要です。
犬が求めてきた時ではなく、飼い主のタイミングで関わるように意識することで、健全な主従関係と適度な距離感を築くことにつながります。
問題行動は声を荒げて叱ってはいけない?
留守番中に部屋を荒らされたり、粗相をされたりしたのを発見すると、感情的に叱りたくなりますが、これは逆効果です。犬は時間が経ってから叱られても、何に対して怒られているのかを理解できません。
それどころか、「飼い主が帰ってくると怖いことが起きる」と学習してしまい、不安をさらに増大させたりする悪循環に陥ります。分離不安による問題行動は、犬がわざとやっているわけではなく、不安やパニックによるものです。
叱るのではなく、その行動の根本原因である不安を取り除くための対策を考える必要があります。
多頭飼いで犬の分離不安症は改善する?
寂しさを紛らわすために、新しく犬を迎え入れる「多頭飼い」を検討する飼い主もいますが、これは慎重に判断すべきです。分離不安症の原因が「飼い主と離れること」への不安である場合、ほかの犬がいてもその不安は解消されません。
むしろ、新しい犬の存在がストレスになったり、先住犬との相性が悪かったりすると、問題はさらに複雑化する恐れがあります。分離不安の解決策として、安易に多頭飼いを始めるのではなく、まずは今いる愛犬の問題と向き合い、専門家のアドバイスを受けながら解決の道を探るのが賢明です。
犬の分離不安症の治療│専門家への相談も検討
犬が分離不安の症状が深刻で日常生活に支障が出ている場合は、専門家の助けを借りることを強く推奨します。愛犬の状態に合わせた具体的な解決策を見出すことにつながるでしょう。
動物病院で身体的な病気がないか確認
犬の分離不安症にみえる行動が、実は別の身体的な病気によって引き起こされている可能性も考慮しなくてはなりません。
たとえば、粗相は泌尿器系の疾患、震えは神経系の病気、破壊行動は痛みや不快感からくるストレスが原因であることもあります。そのため、行動の問題に取り組む前に、まずは動物病院で全身の健康チェックを受けることが不可欠です。
獣医師やドッグトレーナーに相談
分離不安症の治療は、獣医師と行動の専門家であるドッグトレーナーが連携して進めるのが最も効果的です。特に、犬の行動治療を専門とする「行動診療科」を設けている動物病院では、より踏み込んだカウンセリングや治療プログラムの提案が受けられます。
獣医師が診断と必要に応じた薬物療法を行い、ドッグトレーナーがその診断に基づいた具体的なトレーニングプランを作成し、飼い主をサポートします。一人で抱え込まず、専門家の客観的な視点と知識を借りることが、問題解決への確実な一歩となります。
犬を落ち着かせる薬やサプリも
犬の不安やパニックのレベルが非常に高く、トレーニングを受け入れられる精神状態にない場合、獣医師の判断で抗不安薬や抗うつ薬といった向精神薬が処方されることがあります。
これらの薬は、犬の過剰な不安感を和らげ、心を落ち着かせることで、行動修正トレーニングの効果を高めることを目的としています。
薬物療法は、かならず専門家であるトレーナーなどによる行動療法とセットで行われるべきものであり、薬だけで治すものではありません。使用にあたっては、かならず獣医師の指示に従い、用法・用量を守る必要があります。
まとめ│犬の分離不安症は重症化するまえに対処しよう
犬の分離不安症は、飼い主と離れることへの強い不安が原因で、物を壊す、吠え続ける、粗相をするといったさまざまな問題行動を引き起こす心の病気です。
もしも分離不安の症状が重い場合や、家庭での対応だけでは改善がみられない場合は、愛犬を苦しみから救うためにも、動物病院やドッグトレーナーなどの専門家に相談してみましょう。
愛犬ブリーダーでは、犬と人の幸せな暮らしをサポートするため、お役立ち情報をコラムとして発信しています。
子犬をお迎えしたいと考えている方は、犬のプロであるブリーダーからのお迎えがおすすめ!犬種や毛色などから探せる検索機能をぜひご利用ください。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、犬のしつけインストラクター、少額短期保険募集人の資格を保有。豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら
人気の記事
新着記事