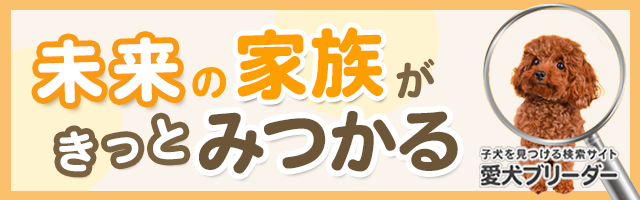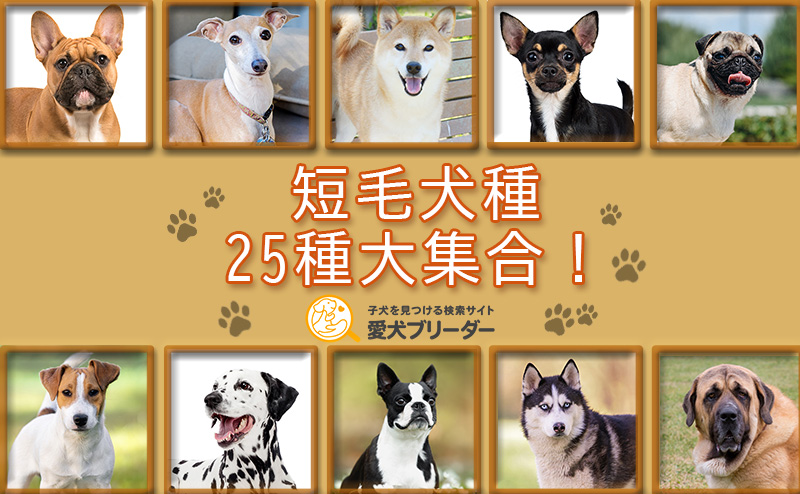犬の耳掃除完全マニュアル!ベストな頻度から注意点まで徹底解説!
公開日:2025年9月12日
更新日:2025年9月16日

愛犬の健康を守るためのケアの中でも、耳掃除は特に大切なものの一つです。
しかし、どのくらいの頻度で、どんな方法でお手入れすれば良いのか、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、自宅でできる安全な耳掃除のやり方から、適切な頻度、注意点、そして動物病院へ行くべきサインまで解説していきます。
[目次]
犬の耳掃除はしないほうがいいって本当?
「犬の耳掃除はしないほうがいい」と聞いたことがあるかもしれません。
確かに、犬の耳には自浄作用があり、健康な状態であれば頻繁な手入れは不要なことが多いですが、掃除がまったく必要ないわけではありません。
犬種や体質、生活環境によっては汚れがたまりやすく、トラブルの原因になる場合もあります。大切なのは、やりすぎないことです。
定期的に耳の中をチェックして、汚れが目立つ場合に適切なお手入れを行うのが理想的です。
犬の耳掃除をしないとどうなる?
犬の耳掃除を怠ると、さまざまな耳のトラブルを引き起こす可能性があります。
犬の耳道はL字型に曲がっており、構造上、通気性が悪く、湿気や汚れがたまりやすい特性をもっています。
この環境は、細菌や真菌にとって繁殖しやすい温床となり、特に「外耳炎」のリスクを高めます。放置すると炎症がさらに悪化し、「中耳炎」や「内耳炎」といったより深刻な病気に発展する可能性もあります。
定期的な耳のチェックで異変に気づき、適切なケアを施すことが大切です。
耳掃除が欠かせない犬種は?
特に注意が必要なのは 垂れ耳の犬種 です。
耳が垂れていると穴がふさがりやすく、内部が蒸れて細菌やカビが繁殖しやすくなります。代表的なのは、アメリカンコッカースパニエルやダックスフンド、ラブラドールレトリーバーなどです。
また、皮膚にシワが多い犬種(パグ・フレンチブルドッグなど)は、耳のまわりのシワに汚れや湿気がたまりやすいので注意が必要です。
さらに、耳の中に毛が多い犬種(プードル・シュナウザーなど)は通気性が悪く、耳垢や汚れがたまりやすくなります。
そのほか、子犬(免疫力が未熟)や老犬(体力が低下している) も耳のトラブルが起こりやすいため、こまめな耳チェックを習慣にしましょう。
犬の耳掃除の頻度はどれくらいが正解?
愛犬の耳掃除の適切な頻度は、犬種や耳の状態によって大きく異なります。
ここでは、耳掃除の基本的な頻度の目安と、やりすぎによるリスクについて解説します。
健康な耳なら月に1〜2回が目安
特に目立った汚れや臭いがなく、健康な状態の犬であれば、耳掃除の頻度は月に1〜2回程度で十分です。
ただし、これはあくまで目安であり、すべての犬に当てはまるわけではありません。
大切なのは回数を決めて行うことよりも、耳の中をチェックする習慣をつけることです。
散歩の後やブラッシングのついでに、耳をめくって中を見てみましょう。その際に汚れが気になったら、軽く拭き取る程度のお手入れをします。
季節や体調によっても耳の状態は変わるため、愛犬の様子にあわせて柔軟に対応しましょう。
耳掃除のやりすぎで起こるトラブルに注意
愛犬を思うあまり、耳をきれいにしすぎることは逆効果になる可能性があります。
頻繁な耳掃除や、ゴシゴシと強くこする行為は、耳の皮膚を守っている常在菌や皮脂まで取り除いてしまいます。
これにより、皮膚のバリア機能が低下し、かえって炎症や感染症を引き起こしやすくなるのです。
また、綿棒などを耳の奥まで入れてしまうと、繊細な耳道を傷つけたり、最悪の場合は鼓膜を損傷させたりする危険も伴います。
掃除の後に愛犬が耳を痛がる、赤みや血がみられるといった場合は、すぐに動物病院を受診してください。
自宅でできる!犬の耳掃除の安全なやり方

愛犬の耳掃除は、ポイントをおさえれば自宅でも安全に行うことができます。
ここでは、準備する道具から具体的な手順まで、初心者の方でも安心してできる耳掃除のやり方を紹介します。
犬の耳掃除の前に準備するもの
自宅で犬の耳掃除をする際は、まず必要なものをそろえましょう。
- 犬用の洗浄液(イヤークリーナー/イヤーローション)
耳垢をやわらかくして汚れを浮かせる効果があります。 - 柔らかいガーゼやコットン
洗浄液を染み込ませて汚れをやさしく拭き取ります。 - 耳掃除用シート
指に巻いて使える市販のタイプ。手軽で初心者にもおすすめです。
ティッシュは繊維が硬く、耳を傷つけるおそれがあるため避けましょう。
準備が整ったら、愛犬がリラックスできる環境で耳掃除を始めると安心です。
①耳の入り口周辺を優しく拭き取る
耳掃除の最初のステップは、見える範囲の汚れをきれいにすることです。
まず、コットンやガーゼに洗浄液をたっぷりと染み込ませます。
それを人差し指に巻きつけ、耳の入り口や、ひだがあって汚れがたまりやすい耳介を優しく拭いていきましょう。
このとき、力を入れすぎないのがポイントです。
ゴシゴシこするのではなく、撫でるように汚れをぬぐい取ります。
この段階で耳の奥の汚れが気になっても、無理に指を押し込んではいけません。
あくまでも、目で見て確認できる範囲のケアにとどめてください。
②洗浄液(イヤークリーナー)を使って耳の中を洗浄
耳の入り口がきれいになったら、次は耳道の洗浄です。
まず、愛犬が動かないように頭を優しく支えます。
そして、洗浄液のボトルを耳の穴に近づけ、数滴垂らし入れます。
このとき、ボトルの先端が耳に直接触れないように注意してください。雑菌が繁殖する原因になります。
シャワーのお湯や水、人間用のシャンプーなどを直接耳に入れるのは、外耳炎や中耳炎を引き起こす危険があるため絶対にやめましょう。
スプレータイプの洗浄液を使う場合は、犬が音に驚かないように少し離れた位置から噴射しましょう。
犬にやさしいおすすめの洗浄液は?
愛犬の耳掃除に使う洗浄液は、ワンちゃんの耳にやさしいものを選んであげることが大切です。
製品選びのポイントは、「低刺激」「ノンアルコール」「天然由来成分」であることです。天然由来のラベンダー油やオーツ麦エキス、植物抽出成分などが配合されている製品は、安心して使えると評判です。
また、植物由来成分100%で無香料、無刺激にこだわった製品も人気を集めています。愛犬が嫌がりにくい無香料タイプや、液だれしにくいジェルタイプも使いやすいでしょう。
特に、獣医師監修の洗浄液は、低刺激でありながら消臭や除菌効果も期待できるので、選択肢の一つとして検討してみてください。
耳の汚れがひどい場合は動物病院で相談し、適切な洗浄液を選んでもらいましょう。
③耳をブルブルさせて汚れを外に出す
洗浄液を耳の中に入れたら、すぐに拭き取らずに、耳の付け根(耳たぶの下の軟骨部分)を指で優しくマッサージします。
「クチュクチュ」という音が聞こえるくらいの力加減で、30秒ほど揉み込んでください。
こうすることで、洗浄液が耳道全体に行き渡り、こびりついた耳垢がふやけて浮き上がってきます。
マッサージが終わったら、一度手を放して、犬が自分で頭をブルブルと振るのに任せましょう。
この遠心力で、中の汚れと余分な液体が外に排出されます。
最後に出てきた汚れを、きれいなコットンやガーゼで優しく拭き取れば完了です。
犬の耳を傷つけるNGな掃除方法

愛犬の耳をきれいにしたいという気持ちから、ついやってしまいがちなNGな掃除方法があります。ここでは、愛犬の耳を守るために絶対に避けるべき掃除方法について解説します。
綿棒を耳の奥まで入れるのは危険
人間の耳掃除でよく使われる綿棒ですが、犬に使う際には細心の注意が必要です。
特に、耳の奥深くまで綿棒を挿入する行為は絶対にやめましょう。
犬の耳道はL字型にカーブしているため、まっすぐな綿棒では汚れをきれいにかき出すことができず、逆に耳垢を奥へと押し込んでしまう可能性があります。
さらに、耳の皮膚は非常にデリケートなため、綿棒でこすることで傷つけてしまったり、手元が狂って鼓膜を損傷させてしまったりするリスクも伴います。
もし綿棒を使うのであれば、耳の入り口のヒダなど、見える範囲の汚れを軽くぬぐう程度に限定してください。
人間用のウェットティッシュや消毒液はNG
犬の皮膚は人間よりも薄くデリケートなため、人間用の製品を使うのは避けましょう。
たとえば、人間用のウェットティッシュや消毒液には、アルコール成分が含まれていることが多く、犬の皮膚には刺激が強すぎて炎症やかぶれの原因になります。
これは赤ちゃん用のおしりふきも同様です。
また、インターネットなどで見かける重曹を使った洗浄なども、犬の皮膚のpHバランスを崩してしまうおそれがあります。
かならず犬専用に開発された、安全な洗浄液や耳掃除シートを使用してください。
獣医師の指示なく耳毛を抜くのは避ける
トイプードルやシーズーなど、犬種によっては耳の中に毛が生えていることがあります。
この耳毛が多すぎると、耳の通気性を悪くしてトラブルの原因になる場合もありますが、獣医師の指示なく自己判断で抜くのはやめましょう。
耳毛には、ホコリなどの異物が耳の奥に入るのを防ぐという大切な役割もあります。
無理に毛抜きや鉗子を使って抜くと、毛穴を傷つけてしまい、そこから細菌が感染して炎症を起こすリスクがあります。
耳毛の処理が必要かどうかは、犬の状態によって異なりますので、まずはかかりつけの動物病院で相談することをおすすめします。
耳掃除を嫌がる犬を上手に慣らすコツ
耳掃除をしようとすると、逃げたり暴れたりして嫌がるワンちゃんは少なくありません。
ここでは、犬がリラックスして耳掃除を受け入れられるようになるための、上手な慣らし方のコツを紹介します。
①耳を触られることに慣れさせる
いきなり耳掃除の道具を見せたり、耳に液体を入れたりするのではなく、まずは「耳に触られること」に慣れてもらうことから始めましょう。
普段、愛犬を撫でてリラックスさせているときに、何気なく耳にそっと触れてみてください。
最初は耳の付け根や外側から始め、嫌がるそぶりを見せなければ、耳を優しくめくったり、軽く揉んでみたりします。
このとき、「いい子だね」と穏やかな声で褒めてあげることがポイントです。
これを毎日少しずつ繰り返すことで、耳を触られることへの警戒心を解き、ケアを受け入れるための土台を作ります。
②ごほうびを使いながらポジティブな印象をつける
耳に触られることに慣れてきたら、次のステップとして「耳のケア=良いことがある」というポジティブな印象を関連付けていきましょう。
耳を少し触ったら、すぐに褒めたりごほうびをあげたりしてみましょう。
これを繰り返して、犬が喜んで耳を触らせてくれるようになったら、今度はコットンを見せる、コットンの匂いを嗅がせる、コットンを耳に軽く当てる、といったように少しずつ段階を進めていきます。
各ステップをクリアするたびに、必ず褒めてごほうびをあげるのがコツです。
焦らずに愛犬のペースにあわせて、楽しいトレーニングの時間にしましょう。
③どうしても嫌がる場合は動物病院に相談
いろいろ試してみても、どうしても耳掃除を嫌がる、あるいは恐怖でパニックになって暴れてしまう場合は、無理に自宅でケアをつづけるのはやめましょう。
飼い主がケガをする危険があるだけでなく、愛犬にトラウマを植え付けたり、おさえつけることで体を痛めてしまったりする可能性もあります。
安全にケアができないと感じたら、動物病院やトリミングサロンといったプロに相談するのが賢明です。
耳垢でチェック!動物病院へ行くべきサイン

毎日の耳チェックは、愛犬の健康状態を知るための重要なバロメーターになります。
耳垢の色や量、臭いがいつもと違う場合、それは何らかの病気のサインかもしれません。
ここでは、特に注意したい耳のトラブルのサインを具体的に解説します。
黒くてベタベタした耳垢|耳ダニの疑い
コーヒーの粉のような、黒くてカサカサ、あるいはベタベタした耳垢が大量に出ている場合、「ミミヒゼンダニ(耳ダニ)」という寄生虫の感染が疑われます。
耳ダニの感染は非常に強いかゆみを引き起こすため、愛犬は頭を激しく振ったり、後ろ足でしきりに耳を掻いたり、家具や床に耳をこすりつけたりするようになります。
この病気は感染力がとても強く、散歩中などにほかの犬からうつることがあります。
同居しているペットがいる場合は、そちらにも感染している可能性が高いので、症状がみられたら速やかに動物病院で診察を受けましょう。
茶色の耳垢|マラセチア感染の可能性
茶色やこげ茶色のベタベタした耳垢がみられ、独特の甘酸っぱいような、発酵したような臭いがする場合、マラセチアという真菌(カビの一種)が原因の「マラセチア性外耳炎」の可能性があります。
マラセチアは健康な犬の皮膚にも存在する常在菌ですが、アレルギーや皮脂の過剰分泌、湿度の高い環境などが原因で異常に増殖すると、炎症を引き起こします。
強いかゆみや耳の赤みを伴うことが多く、特に垂れ耳の犬種によくみられる病気です。
自然に治ることは少ないため、獣医師による適切な治療が必要です。
黄色い膿のような耳垢|細菌感染のサイン
黄色や緑がかった、膿のような粘り気のある耳垢が出ているときは、細菌感染による化膿性の外耳炎が考えられます。
この場合、強い不快な臭いを伴うことが多く、耳の皮膚が赤く腫れて熱を持ったり、痛みのために触られるのを極端に嫌がったりします。
耳の中に傷ができた、異物が入った、あるいはマラセチア感染が悪化した場合などに、ブドウ球菌などの細菌が二次感染を起こすことで発症します。
原因となっている細菌を特定し、それに合った抗生剤などでの治療が必要になるため、家庭でのケアでは対応できません。すぐに動物病院を受診するようにしましょう。
異臭がしたり首を傾けたりする場合も要注意
健康な耳からは、ほとんど不快な匂いはしませんが、外耳炎や中耳炎、内耳炎などの炎症が起こると悪臭を放つようになります。
具体的には、真夏の生ゴミのような腐敗臭や、酸っぱくて油っぽい匂い、発酵したような匂い、汗臭い匂い、ツンとした刺激臭など、さまざまな異臭が挙げられます。
また、頻繁に首を傾けるしぐさ(斜頸)がみられる場合、外耳炎が悪化して中耳や内耳まで炎症が及んでいる可能性があります。
内耳は体のバランスを司る三半規管があるため、炎症が起こると平衡感覚に異常が生じ、首を傾げたり、同じ場所をぐるぐる回ったり(旋回運動)、目が揺れたり(眼振)といった神経症状が出ることがあります。
もし愛犬の耳からこのような異臭がしたり、頻繁に耳を掻いたり、頭を振ったりするような行動がみられたりする場合は、すぐに動物病院を受診してください。
早期に適切な治療を開始することで、症状の悪化を防ぎ、愛犬の耳の健康を守ることができます。
まとめ|犬の耳掃除は“やりすぎない+正しい方法”がカギ!
愛犬の耳の健康を保つためには、日々の観察と適切なケアが不可欠です。
健康な耳であれば頻繁な掃除は必要なく、やりすぎはかえってトラブルの原因になることも。基本は「汚れていたら、見える範囲を優しく拭く」というスタンスで十分です。
愛犬の様子に少しでも異常を感じたら、自己判断せずに速やかに獣医師に相談することが、愛犬の耳を守るための最も重要なポイントです。
愛犬ブリーダーでは、犬と人の幸せな暮らしをサポートするため、お役立ち情報をコラムとして発信しています。
子犬をお迎えしたいと考えている方は、犬のプロであるブリーダーからのお迎えがおすすめ!犬種や毛色などから探せる検索機能をぜひご利用ください。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、犬のしつけインストラクター、少額短期保険募集人の資格を保有。豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら
人気の記事
新着記事