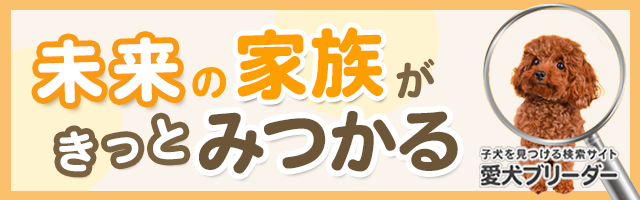盲導犬にやってはいけない5つのこと!その理由や正しい接し方とは?
公開日:2025年8月1日
更新日:2025年8月12日

街なかで盲導犬をみかけた際、どう接すれば良いか迷った経験はありませんか?
盲導犬は視覚に障がいのある方の「目」となり、安全な歩行をサポートする大切なパートナーです。
この記事では、盲導犬の役割から、やってはいけないこととその理由、そして盲導犬ユーザーへの適切なサポート方法まで、詳しくご紹介します。
[目次]
盲導犬ってどんな存在?
盲導犬は、視覚障がいのある方々が安全に、そして快適に外出できるようサポートする、特別な訓練を受けた犬たちのことです。
彼らは単なるペットではなく、「身体障害者補助犬法」に基づいて認定された、ユーザーにとってかけがえのない存在です。
盲導犬のお仕事とは
盲導犬の主な仕事は、視覚障がいのある方が安全に歩けるようサポートすることです。
具体的には、道路の端に沿ってまっすぐ歩くこと、交差点や段差の手前で止まること、電柱や看板などの障害物をよけることなどが挙げられます。
盲導犬ユーザーは、頭の中で目的地までの道順を思い描きながら盲導犬に指示を出し、盲導犬は、ハーネスをとおして体の動きや停止などで、段差や障害物の存在をユーザーに知らせます。ユーザーはその微細な動きを手に感じ取り、状況を判断しながら歩いています。
このように、盲導犬とユーザーは共同作業で安全な歩行を実現しているのです。
盲導犬の法的な位置づけは?
盲導犬は「身体障害者補助犬法」(平成14年10月施行)に基づき、公共施設や交通機関はもちろん、飲食店やホテル、タクシーなどの一般的な施設でもユーザーと一緒に利用することが認められています。
この法律は、補助犬を使う身体障がい者の自立と社会参加を促進することを目的としています。いまだに盲導犬の同伴を拒否されるケースもありますが、このような拒否は法律違反となる可能性があります。
盲導犬はペットではなく、法律上、障がいのある方の身体の一部として扱われるため、一般の方が利用できる場所では同伴が可能です。
盲導犬になるまでの訓練とは?
盲導犬になる犬たちは、厳しい基準を満たしたうえで約6か月~1年間の特別な訓練を受けます。
生後2か月~1歳までは「パピーウォーカー」と呼ばれるボランティアの家庭で、人との生活ルールや社会性を身につけます。
その後、盲導犬協会に戻り、性格を評価する「稟性評価(りんせいひょうか)」が行われます。訓練では、まず「シット(座れ)」「ダウン(伏せ)」「ウェイト(待て)」などの基本的な指示を、褒めることを通して楽しく学習します。
基本訓練の後は、ハーネスを装着して障害物をよけたり、段差や交差点を知らせたりする「誘導訓練」が行われます。この訓練では、ユーザーの指示が危険につながると判断した場合に、指示に従わず安全を優先する「不服従訓練」も含まれます。
訓練の最終段階では、訓練士がアイマスクを着用して実際の歩行を評価し、盲導犬としての適性が最終的に判断されます。
最後に、盲導犬を希望する視覚障がい者と犬が約4週間の「共同訓練」を行い、お互いの信頼関係を築きながら実際の生活に必要なスキルを習得します。
パピーウォーカーにはどうしたらなれるの?
パピーウォーカーになるには、盲導犬協会が設けているいくつかの条件を満たす必要があります。協会ごとに多少異なる場合もありますが、一般的には以下のような内容です。
- 訓練センターの近くに住んでいること
- 車を所有していて犬を送迎できること
- 月1回程度のレクチャーに参加できること
- 室内で子犬を安全に飼育できる環境があること
- 子犬優先で過ごせる時間的な余裕があること
- 家族全員が犬を迎えることに同意し、協力的であること
- 現在、ほかの犬を飼っていないこと
- 集合住宅の場合、管理側の承諾が得られていること
また、協会によっては、子犬のフードや日用品、治療費などに対して月数千円程度の費用負担が発生する場合もあります。
詳細は事前に各協会へ確認するのがおすすめです。
盲導犬にやってはいけない5つの行動とその理由

盲導犬たちは、盲導犬ユーザーの目として集中して仕事をしています。そのため、盲導犬が仕事に集中できなくなるような行為は避けることが大切です。
特に、以下の5つの行動は盲導犬の仕事を邪魔してしまう可能性があるため、注意しましょう。
①盲導犬に話しかけたり音を出したりする
盲導犬は前方にある障害物や人の流れ、交差点などの道路状況に注意を払いながら非常に集中して歩いています。
「かわいいね」「お利口だね」などと声をかけたり、口笛を吹いたりして盲導犬の気を引くと、盲導犬がそちらに意識を向けてしまい、よそ見をする可能性があります。
これにより角や段差を見落としたり障害物の発見が遅れたりして大きな事故や道に迷う原因につながるケースも考えられます。
盲導犬が仕事に集中し、ユーザーと安全に歩行できるよう遠くから静かに見守りましょう。
②盲導犬に食べものをみせる・与える
盲導犬の食事や水分は、盲導犬ユーザーが健康管理を考え、決まった時間と量で与えています。
ほかの人が勝手に食べものを与えてしまうと、盲導犬の排泄リズムや体調を崩す原因になるだけでなく、集中力を削いでしまう可能性もあります。
盲導犬は訓練によって、外では食べものを欲しがらないようにしつけられていますが、ユーザーに無断で食べものを与えたり、みせたりすることは避けましょう。
③盲導犬に触れる
盲導犬がハーネス(胴輪)を着けているときは、仕事中であることを示しています。
たとえ何もしていないようにみえても、盲導犬は周囲の状況に常に気を配っています。そのため、盲導犬に触れる行為は集中力を途切れさせてしまう原因となります。
ユーザーと盲導犬が安全に歩行できるよう、むやみに触ったり撫でたりすることは避けましょう。
④盲導犬を凝視する
盲導犬は人が大好きな性格の犬が多いため、じっと目をみつめられるとうれしくなってしまい、仕事に集中できなくなる可能性があります。
たとえば、「ウェイト(待て)」と指示されて待っているときでも、じっとみつめられると、その場から動いてしまう可能性も考えられます。
そうなるとユーザーが戻ってきたときに、どこに盲導犬がいるのか、わからなくなり困る事態につながりかねません。
盲導犬が仕事に集中できるよう、凝視することは避けましょう。
⑤盲導犬の写真を勝手に撮る
盲導犬の写真を勝手に撮ったり、SNSに載せたりする行為は控えましょう。
盲導犬はユーザーのプライベートな部分にかかわる大切な存在であり、勝手に撮影されることでユーザーが不快に感じる場合があります。
また、フラッシュなどの光は盲導犬の集中力を乱す可能性も考えられます。
盲導犬ユーザーが助けを求めているサインは?

盲導犬と歩いているユーザーは、基本的には見守ることが大切ですが、周囲のサポートが必要な場面もあります。
ここでは、ユーザーが助けを求めているサインについてご紹介します。
信号で立ち止まっているとき
信号機のある横断歩道で立ち止まっているとき、ユーザーは信号の色を判断するために、周囲の車の音や人の動きなどを注意深く聞いています。
しかし、音響信号がない交差点では、周囲の音だけでは判断が難しいこともあります。
盲導犬は信号の色を判断できないため、ユーザーが「赤ですよ」「青になりましたよ」といった声かけを必要としている場合があります。
もしユーザーが横断歩道で戸惑っている様子であれば、「何かお手伝いしましょうか?」「信号は青ですよ」などと、具体的に声をかけてみましょう。
道に迷っているとき
ユーザーが困っているような様子や焦っている場面をみかけた場合、道に迷っている可能性があります。
駅のコンコースのような広い場所や、人混みの多い場所では、周囲の状況を把握するのが難しく、立ち往生してしまうことも考えられます。そのようなときは、「何かお手伝いしましょうか?」と声をかけてみましょう。
もし道に迷っているようであれば、目的地やユーザーが知っている場所まで案内してあげると親切です。
道案内をする際は、後述する「手引きの歩行」でサポートすると良いでしょう。
転倒・衝突など危険が迫っているとき
盲導犬や盲導犬ユーザーは見守る姿勢が大切ですが、危険な状況に遭遇した場合は、大きな声で制止することも重要な行動です。
たとえば、ユーザーが道路に飛び出しそうになっている、電車のホームから足を踏み外しそうになっている、自転車が近づいているの気付いていないなど、危険が迫っていると感じたら、迷わず「危ない!」などと大きな声で知らせましょう。
ユーザーと盲導犬の安全を守るためにも、瞬時の判断と行動が求められる場面です。
私たちが盲導犬ユーザーにできること
盲導犬ユーザーを街でみかけたとき、私たちはどうすればサポートできるのでしょうか。ここでは、具体的なサポート方法と、その際のポイントについてご紹介します。
道案内をサポートするときのポイント
道案内をサポートする際は、手引きの歩行が基本的な方法です。
これは、案内する人がユーザーの半歩前を歩き、ユーザーがその人の腕や肩を軽くつかむことで、安心して移動できるようにする方法です。
段差や階段、曲がり角などで立ち止まり、上がります右に曲がりますなどと具体的に声をかけることで、ユーザーは状況を把握しやすくなります。
腕を引っ張ったり、後ろから押したりして誘導するのは、かえって危険な場合があるので避けましょう。
また、目的地までの道順をすべて知らなくても、今いる場所の様子を伝えたり、ユーザーが知っている場所まで案内したりするだけでも、大きな助けになります。
声をかけるタイミングと注意点
盲導犬ユーザーに声をかける際は、タイミングと方法が重要です。
ユーザーは周囲の音で状況を判断しているため、雑踏の中や少し距離が離れていると、自分に話しかけられていることに気付かない場合があります。「何かお手伝いしましょうか?」と優しく、そしてはっきりと声をかけましょう。
声をかける相手は盲導犬ではなく、かならずユーザー本人です。
盲導犬の名前を尋ねて、それを呼びかけるのは絶対にやめましょう。これは盲導犬の集中力を乱し、ユーザーの安全を脅かすことにつながります。
SNSでもできる啓発活動
盲導犬への理解を深めるためには、私たち一人ひとりの啓発活動も大切です。
たとえば、SNSを通じて盲導犬に関する正しい知識や、やってはいけないこと、適切な接し方などを発信することで、より多くの人に盲導犬への理解を広めることができます。
また、日本盲導犬協会などの団体では、盲導犬の育成を支援するための募金活動やボランティアを募集しています。
募金箱への協力や、インターネットを通じた寄付など、さまざまな形で支援に参加することも、盲導犬ユーザーの社会参加を後押しすることにつながります。
盲導犬への理解を深めよう

盲導犬と盲導犬ユーザーが安心して社会で暮らすには、私たち一人ひとりが盲導犬について正しく理解することが不可欠です。
「盲導犬はかわいそう」は誤解?
盲導犬はかわいそう、ストレスが多い、自由に遊べない、といったイメージをもつ人もいるかもしれませんが、これは大きな誤解です。
盲導犬はユーザーの目として共に生活し、仕事をしていることに喜びを感じています。必要なケアが習慣化されており、仕事が終わればリラックスして普通のペットのように遊んだりもします。
日本盲導犬協会も「盲導犬は大好きなユーザーのそばにいて、日々楽しく歩く幸せな犬たちだ」と伝えています。かわいそうという誤解は、ユーザーを悲しませてしまう可能性があります。
盲導犬はユーザーの生活に彩りを添えるかけがえのないパートナーなのです。
盲導犬の見分け方は?
盲導犬は、介助犬や聴導犬といったほかの補助犬と区別するために、特定の表示を身につけています。
盲導犬は、白や黄色の「ハーネス(胴輪)」を身につけており、外からみて「盲導犬」と表示されているのが特徴です。
また、ユーザーは「認定証(使用者証)」を携帯することが義務付けられています。もし、表示がない犬や認定証の提示に応じない場合は、補助犬ではない可能性があります。
盲導犬の入店・同伴ルール
盲導犬は身体障害者補助犬法により、公共施設や公共交通機関、飲食店、ホテルなど不特定多数の人が利用する施設への同伴が義務付けられています。
これは、盲導犬ユーザーが安心して社会参加できるための重要なルールです。
盲導犬は静かにユーザーのそばで待機できるよう訓練されています。
万が一、盲導犬の入店を拒否された場合は、法律で同伴が認められていること、ペットではなく盲導犬であること、きちんと訓練をけていることなどを、お店の方に伝える必要があります。
まとめ|盲導犬にやってはいけないことは、盲導犬の注意をそらす行為!
盲導犬は、日々真剣に仕事に取り組んでいます。そのため、盲導犬にやってはいけないことは、その集中力を妨げるすべての行為です。
盲導犬への正しい理解を深め、温かく見守り、必要な場面では手を差し伸べることで、誰もが暮らしやすい社会につながっていくでしょう。
愛犬ブリーダーでは、犬と人の幸せな暮らしをサポートするため、お役立ち情報をコラムとして発信しています。
子犬をお迎えしたいと考えている方は、犬のプロであるブリーダーからのお迎えがおすすめ!犬種や毛色などから探せる検索機能をぜひご利用ください。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、犬のしつけインストラクター、少額短期保険募集人の資格を保有。豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら
飼い方の関連記事
飼い方の記事一覧を見る人気の記事
新着記事