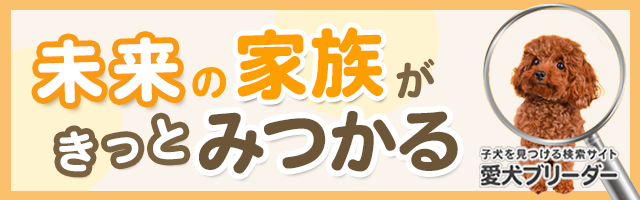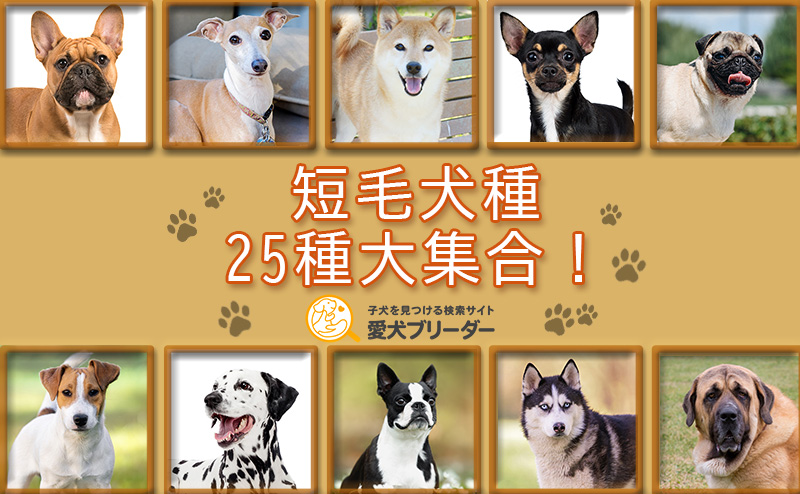犬の散歩の適切な回数と時間は?毎日必要?「しつけ」のプロが教えるマナーと注意点
公開日:2025年11月20日
更新日:2025年11月25日

犬を散歩させることは、愛犬の心と体の健康を維持するために欠かせない日課です。
しかし、散歩の頻度や必要な時間、何歳から始めれば良いのかなど、悩む飼い主も少なくありません。
この記事では、犬に関する資格を持つ専門家が監修し、犬種や年齢に応じた散歩の適切な時間や回数の目安、しつけの観点からみたマナー、そして季節ごとの注意点などを解説します。
毎日の散歩を安全で楽しいものにするためのポイントを確認しましょう。
[目次]
犬の散歩はなぜ毎日必要?しないとどうなる?

犬にとって散歩は、運動や排せつのためだけでなく、心と体の健康を保つ大切な時間です。
毎日の散歩で適切な運動量を確保し、犬の本能である「探索欲」をクン活と呼ばれる匂いを嗅ぐ行為で満たしたり、ほかの犬との交流を通じて、精神的な刺激を得られます。
逆に散歩をしないと、運動不足で肥満や関節のトラブルを抱えたり、ストレスから噛み癖や無駄吠えなどの問題行動につながることがあります。
犬にとっての散歩のメリットを簡単にまとめましたので参考にしてください。
| 元気な体づくり | 適度な運動で太りすぎを防ぎ、 足腰が丈夫になります。 |
| ストレス解消 | 外の空気や匂いを嗅いで、家では得られない刺激を受けストレスが軽減されます。 |
| 社会性の発達 | ほかの犬や人、さまざまな環境に慣れることで協調性を高めます。 |
| 楽しい情報収集 | さまざまな匂いを嗅ぐことは犬にとって重要な情報収集活動であり、脳を活性化させます。 |
| 信頼関係の強化 | 飼い主と一緒に散歩することで、 安心感が増し絆が深まります。 |
また、自然の中を歩くことや楽しそうな姿を見て癒されたり、生活リズムを整えられるなど、飼い主にとってもメリットがあるといえるでしょう。
【犬種別】愛犬に必要な散歩時間は?
犬に必要な散歩時間は、犬種やその個体がもつ体力によって大きく異なります。
目安として1日に1~2回が基本ですが、散歩後に疲れすぎていないか、反対に物足りなさそうにしていないかを確認して、愛犬にとっての最適な時間をみつけることが重要です。
体の大きさごとに、適切とされている散歩時間や距離、回数をまとめました。
| 犬の サイズ |
時間 (1回) |
回数 (1日) |
距離 (1日) |
主な犬種 |
|---|---|---|---|---|
| 小型犬 | 15〜30分 | 2回 | 1〜2km | トイプードル、チワワ、ポメラニアン、シーズー |
| 中型犬 | 30〜60分 | 2回 | 2〜4km | 柴犬、ビーグル、コーギー、アメリカン・コッカー・スパニエル |
| 大型犬 | 40〜90分 | 2〜3回 | 3〜6km | ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバー、シベリアンハスキー、スタンダードプードル |
※適切な時間や回数は、年齢や健康状態、性格などによっても変わるため、あくまで目安として参考にしてください。
【年齢別】子犬とシニア犬の散歩で注意すべきNG行動

犬の散歩は、年齢やライフステージによって注意すべきポイントが変わります。
特に社会化期の子犬や、体力が落ちたシニア犬は無理な散歩をするとケガや体調不良につながるでしょう。この章では、子犬とシニア犬それぞれの散歩で気をつけたいポイントや避けるべき行動について解説していきます。
子犬の散歩デビューはワクチン接種後に
子犬の散歩デビューは、ワクチンプログラムが完了してからが基本です。
生後3〜4か月以降が目安ですが、個々のスケジュールに合わせて獣医師に相談し、許可を得てから始めましょう。
また、初めての散歩では地面におろさず抱っこをして、外の音や匂い、景色に慣れさせるようにしてください。
【子犬の散歩で注意すべきポイント】
- 首輪やハーネスが外れないか確認する
- リードの長さを工夫して、あちこち歩かせない
- 地面のものを口に入れないよう注意する
- こわがっている場合は抱っこで慣れさせる
子犬は楽しいことに夢中になると疲れを忘れてはしゃぎ過ぎてしまいます。元気そうに見えてもあとで一気に疲れてしまうことがあるため、1歳前後までの子犬のうちは飼い主が様子を見て切り上げるようにしましょう。
老犬(シニア犬)の散歩は体調を最優先に
シニア犬の散歩は、その日の体調を最優先に考えることが大切です。
長時間歩けない場合も多く、5分程度の短い散歩でも気分転換になることがあります。散歩を嫌がる素振りをみせたら、無理強いは禁物です。
【シニア犬の散歩で注意すべきポイント】
- 関節の負担にならないよう、無理をさせない
- 滑りやすい場所や段差の多い道を避ける
- 気温に敏感のため、夏や冬の体温管理に注意
- 疲れやすいことを理解し、休憩をこまめに取る
- 愛犬のペースに合わせて急かさず歩く
愛犬が安心して自分のペースで歩ける環境を整えることが、シニア期の散歩の質を高めます。
プロが考える散歩のお悩み解消法と守るべきマナー

毎日の散歩は犬との絆を深める大切な時間ですが、リードの引っ張りやほかの犬への吠えなど、悩みを抱える飼い主もいます。
問題行動は、原因を理解し適切に対処することで改善が期待できます。
ここでは、散歩中の悩みの具体的な解消法と、周囲への迷惑をかけないために最低限守るべきマナーを解説します。
リードを引っ張る原因とすぐにできる対処法
犬がリードを強く引っ張る主な原因は、好奇心や興奮、あるいは「飼い主より先に行きたい」という気持ちのあらわれです。引っ張り癖はすぐに直るものではないため根気強く教える必要があります。
対処法として、以下のことをチャレンジしてみましょう。
- 犬がリードを引っ張ったらすぐに立ち止まる
- 飼い主の横に戻り、リードが緩んだら再び歩き出す
- 成功したらすぐに褒める
- 戻ってこない場合はおやつなどで呼び戻す
- 飼い主の声が聞こえない場合は抱っこして落ち着かせる
成功して褒めることを繰り返すことで、飼い主のペースで歩くことを学習しやすくなります。飼い主の声が聞こえていない場合は、抱っこをして落ち着かせるのも効果的です。
散歩中に吠えちゃう!原因と効果的な対応
散歩中に犬や人、車などに吠える行動は、警戒心や興奮、遊びたい気持ちなど、さまざまな原因で起こります。
恐怖や警戒が原因の場合は、対象から距離をとり犬が安心できる状況を作ることが大切です。
吠える前におやつで注意をそらし、吠えなかった行動を褒めましょう。落ち着いていれば良いことがあると学習させることができます。
遊びたい気持ちが原因で吠えてしまう場合も、立ち止まったり抱っこをして犬を落ち着かせましょう。冷静に、一貫した態度で対応を続けることが重要です。
排泄物はどう処理する?守るべきマナーと配慮
散歩中の排泄物の処理は、飼い主が最低限守るべきマナーです。
処理の方法として、おしっこはペットボトルの水で流すのが一般的ですが、ペット用のマナーベルトをつけて散歩させれば、道に流れてしまう心配がなくなります。
うんちは公共のゴミ箱やトイレに捨てるのはマナー違反となるので、かならずビニール袋などに入れて持ち帰り、自宅で処理するようにしましょう。
住宅やお店の入り口などでその素振りがある場合は、ほかの場所に連れていくなどして迷惑になるのを防ぐ必要があります。散歩前に自宅のトイレで排泄を済ませておく習慣をつけると、外出先でのトラブルを減らせます。
周囲の人が快適に過ごせるよう常に配慮を忘れないようにしましょう。
愛犬の命を守る!散歩で絶対に注意すべき危険
楽しいはずの愛犬との散歩には、予期せぬ危険が潜んでいることもあります。
ここでは、散歩中に起こりうる重大な危険と、その予防策について具体的に解説します。
夏の散歩は熱中症の危険大!適切な時間帯とサイン
犬は地面の熱を人より強く感じるため、夏の散歩は熱中症のリスクが高く、時間帯の工夫が欠かせません。アスファルトは朝8時ごろから一気に温度が上がることがあるため、涼しい早朝や日が完全に沈んだ夜の散歩が安全です。
出発前には地面を手で触って温度を確かめ、散歩中はこまめに水分補給を行いましょう。
呼吸が荒くなる、よだれが増える、ふらつくなどの症状がみられた場合は熱中症のサインなので、すぐ散歩を中断し、涼しい場所で体を冷やしつつ必要に応じて動物病院に相談してください。
ペット用のクールリングやクールバンダナ、冷感ベストなどのひんやりグッズを取り入れると、暑さ対策がより万全になります。
以下のサイトは、アスファルトの温度を予測し、お散歩に最適な時間帯を教えてくれます。肉球の火傷や凍傷の予防に、お散歩前の参考にしてみてくださいね。
犬のおさんぽ予報(https://s.n-kishou.co.jp/w/sp/road/roadtemp_top)
誤飲・拾い食いの対策と、してしまったときの対処法
散歩中の拾い食いは、愛犬の命を脅かす危険な行動です。
道端にはタバコの吸い殻、焼き鳥の串、人間の食べ物、除草剤がまかれた草など、犬にとって有害なものが落ちている可能性があります。
対策としては、普段のしつけで「待て」や「ちょうだい」といったコマンドを教え、飼い主の許可なく物を口にしないように訓練することが基本です。慣れた道でも目を離さず、愛犬が何に興味をもっているかを把握できるようにしてください。
万が一危険なものを飲み込んでしまった場合は、無理やり口から出そうとせず、何をどれくらい食べたかをすぐに動物病院へ連絡しましょう。
拾い食いを辞めさせるしつけができるまでは、愛犬が一番気に入っている特別なおやつや音が鳴るおもちゃを持っていき、危険なものから注意を逸らしましょう。
食後の散歩はなぜNGなの?命にかかわる病気のリスク
食後すぐの激しい運動は、犬の命にかかわる病気「胃捻転(胃拡張・胃捻転症候群)」のリスクを高めるため、避ける必要があります。
胃捻転は、胃がガスで膨らみねじれてしまう状態で、特に胸の深い大型犬に多くみられます。血流が滞ってショック状態や呼吸困難を引き起こすケースもあり、発症すると短時間で重篤な状態になる非常に危険な病気です。
胃捻転のリスクを考え、食事は散歩から帰ってきてから与えるか、食後に散歩をする場合は2~3時間以上の休息を確保しましょう。
【お悩み】愛犬が散歩に行きたがらないときの対処法
いつもは喜んで散歩に行く愛犬が、急に行きたがらなくなると心配になるものです。
ここでは、愛犬が再び散歩を楽しいと感じられるようにするための具体的なコツや、飼い主ができる対処方法を紹介します。
愛犬のコンディションに合わせて歩くペースを調整する
犬も体調や気分によって歩くペースが変わります。
元気がないときは無理に歩かせず、短時間で済ませるのも良いでしょう。逆に元気な日は少し長めに歩くなど、日によって調整することで散歩へのストレスを減らせます。雨の日や寒い日など嫌がるタイミングを観察すると、体調や好みの傾向もわかってきます。
また、犬が立ち止まって熱心に匂いを嗅いでいるときは、大事な情報収集中のため、急かさずに待ってあげるようにしましょう。
散歩コースのマンネリ解消法と新しい刺激を与える効果
毎日同じ散歩コースを歩いていると、犬も飽きてしまい、散歩への意欲が低下することがあります。そんなときは、散歩コースやルートを少し変えてみるのが効果的です。
新しい道や場所は、未知の匂いや音、景色にあふれており、犬の好奇心を刺激します。こうした新しい刺激は脳の活性化にもつながり、散歩の楽しみを再発見させるきっかけとなるでしょう。
定期的にコースを見直すことで、マンネリを防ぎ、散歩の質を高めることができます。
【Q&A】飼い主が知りたい!犬の散歩に関するよくある疑問

毎日の犬の散歩には、さまざまな疑問がつきものです。
ここでは、多くの飼い主が抱える散歩に関する素朴な疑問を取り上げ、Q&A形式でわかりやすく回答します。
散歩の時間は毎日同じにしたほうがいい?
散歩時間を毎日きっちり同じにする必要はありません。
むしろ、あまりに規則正しくすると、その時間になると犬が催促して吠えるなどの問題行動につながる可能性もあります。
重要なのは、毎日決まった時刻に散歩へ行くことよりも、1日に必要な運動量をおおむね満たしてあげることです。飼い主の生活リズムの中で、無理なく継続できる時間帯をみつけるのが良いでしょう。
散歩に行くのに適した時間帯は朝と夕方?
散歩の時間帯は季節に合わせて調整することが大切です。
一般的には朝と夕方が適していますが、特に注意したいのは夏と冬です。夏は日中のアスファルトが非常に熱くなり、肉球をやけどしたり、熱中症になる危険があります。早朝や夕方の涼しい時間帯を選ぶと安心です。
いっぽうで、真冬は寒さで体温が急に下がることによるヒートショックのリスクもあります。特に朝晩の冷え込む時間帯は避け、比較的暖かい日中に散歩するのがおすすめです。
散歩は雨や体調不良で毎日行かなくても大丈夫?
犬の散歩は毎日行うのが理想ですが、大雨や台風といった悪天候の日、あるいは犬自身や飼い主の体調が優れない場合には、無理をする必要はありません。
犬の散歩をすることが難しい日は、室内で知育おもちゃを使ったり、飼い主とのコミュニケーションを密にしたりして、運動不足やストレスの解消に努めましょう。何よりも犬の安全と健康を第一に考え、その日の状況に応じて柔軟に対応することが求められます。
散歩に行けないときの運動不足解消法は?
散歩に行けない日は、室内で楽しめる遊びを取り入れてエネルギーを発散させてあげましょう。おもちゃを投げて持ってこさせたり、ロープで引っ張り合いをしたりするだけでも、十分な運動になります。
また、家の中におやつを隠して探させる「ノーズワーク」は、嗅覚を使う頭脳運動として満足度が高く、ストレス解消にも効果的です。
外でしかトイレをしない犬は、短時間だけ外に出して排泄を済ませ、ぬれた体はすぐに拭いて風邪や体調不良を防ぎましょう。
散歩時間が目安より長すぎる・短すぎる場合は?
散歩時間の目安は一般的なものであり、すべての犬に当てはまるわけではありません。目安より短くても、帰宅後に落ち着いて満足しているなら特に問題はありません。
逆に長めの散歩を好む犬でも、表情や歩き方を観察して疲れていないか、足を引きずっていないかを確認しましょう。
散歩の満足度は時間だけで決まるものではなく、匂いを嗅いだり周囲の刺激を楽しむことも大切です。
犬の散歩に必須の便利グッズ9選
最後に、日々の散歩で活躍が期待できるおすすめグッズを紹介します。
愛犬との散歩をより安全で快適にするためには、いくつかの便利グッズをそろえておくと役立ちます。
基本的なリードや首輪・ハーネスはもちろん、水分補給のための水や水飲み、しつけに使うおやつ、雨の日のアイテムなど、準備しておくと便利なアイテムをチェックしてみましょう。
| リード | 普段の散歩では伸縮リードではない普通のリードがおすすめです。犬との距離感を保ちやすく、引っ張り癖のある犬もコントロールしやすいです。 |
| 首輪・ハーネス | ハーネスは首に負担がかからず、安全に散歩ができます。 |
| ウェットティッシュ | 粗相をしたときに便利。人間用のおしりふきでも代用可能です。 |
| うんち袋 | マナーとして必須。散歩中にすぐ取り出せるポーチ付きだと便利です。 |
| 給水ボトル | 特に暑い日や長時間の散歩では、こまめに水分補給できるように持っていきましょう。 |
| 反射材やライト | 朝や夕方、夜間の散歩には視認性アップのため装着。交通事故予防にもなります。 |
| 雨の日グッズ | レインコートや、ペット用の靴で濡らさず快適に。滑りやすい地面で安全に散歩できます。 |
| タオル | 雨や泥でぬれた体や足を拭くのに役立ちます。散歩後のケアが簡単になります。 |
| ひんやりグッズ | 夏の時期には必須です。クールリングなど体温があがるのを防ぎましょう。 |
まとめ|犬の散歩は飼い主との絆づくりにもメリットあり!
犬の散歩は、運動不足の解消やストレス発散だけでなく、私たち飼い主との信頼関係を深める大切な時間です。
犬種、年齢、個体差を考慮して、適切な時間と回数を調整する必要があります。安全やマナーに気をつけながら、ぜひ愛犬との散歩を楽しんでください。
毎日の散歩で健康を守り楽しい時間を共有することで、犬も飼い主も笑顔になれるでしょう。
愛犬ブリーダーでは、犬と人の幸せな暮らしをサポートするため、お役立ち情報をコラムとして発信しています。
子犬をお迎えしたいと考えている方は、犬のプロであるブリーダーからのお迎えがおすすめ!犬種や毛色などから探せる検索機能をぜひご利用ください。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、犬のしつけインストラクター、少額短期保険募集人の資格を保有。豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら
しつけ・散歩の関連記事
しつけ・散歩の記事一覧を見る人気の記事
新着記事