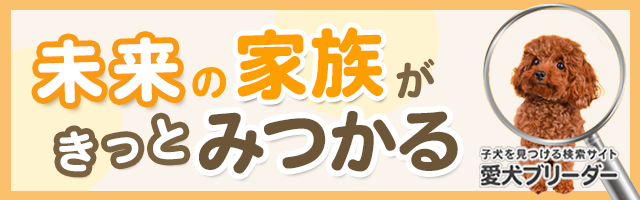子犬の飼い方と迎える準備まとめ|はじめてのお世話・しつけについて
公開日:2025年5月8日
更新日:2025年5月23日

ふわふわで愛らしい子犬との暮らしは、多くの人にとって憧れのひとつ。
でも、子犬を飼いたいとなると「何を準備すればいい?」「しつけはいつから始めるの?」と不安になることも。
この記事では、子犬を迎える前の準備から毎日のお世話、しつけの基本まで、初心者にもわかりやすく解説します。
[目次]
子犬を迎えるための心得
子犬を迎えることは、家族にとって大きな決断であり、単にかわいがるだけでなく、しっかりとした責任と覚悟が求められます。
犬を飼うことは、その一生を預かる飼い主として、毎日の食事や運動、トイレのお世話に加えて、しつけや安全対策、病気の予防まで全ての面倒を見る覚悟が必要です。犬種によって寿命は異なりますが、健康的な生活環境が整えば、家族として長期間ともに暮らすことができます。
赤ちゃんの世話や家族の介護が必要になった際や、飼い主自身が病気やケガをした場合など、子犬の世話が十分にできなくなると、飼い主も犬もつらい思いをしてしまいます。
子犬を飼う前にはしっかりと情報収集し、将来の生活まで見据えて本当に迎え入れる準備が整っているかを十分に検討しましょう。
子犬を迎え入れるときの注意点
子犬を迎える前に、どんな犬種を選ぶかはとても重要なポイントです。見た目のかわいさや好みで決めてしまうと、後々の生活で「思っていたのと違った…」ということにもなりかねません。ここでは、生活スタイルや運動量、毛の抜けやすさなど、犬種選びで確認しておきたいポイントをわかりやすく紹介します。
生活スタイルに合う犬種
犬種によって性格や飼育環境に適した特徴があり、飼い主の生活スタイルや家の環境に合った犬種を選ぶことが大切です。
初めて犬を飼う方には、しつけがしやすいといわれるトイプードルやシーズー、飼い主に従順なパグがおすすめされることもあります。これらの犬種は小型犬で室内飼育にも向くともいわれ、忙しい毎日を送る方や、マンションなど限られたスペースの家で暮らす方にも向いています。また、マルチーズやフレンチブルドッグは、温厚な性格で子どもがいるご家庭にも人気です。
愛犬との共生を考えるなら、家族構成や自宅の広さ、どの程度しつけに時間をかけられるかを考慮して選ぶとよいでしょう。
運動量や散歩の時間を確認
犬の健康維持には適度な運動が欠かせませんが、運動量は犬種ごとに大きく異なります。
たとえば、シベリアンハスキーやコーギー、ゴールデンレトリーバーなどの運動量が多い犬種は、毎日の長時間の散歩や運動が必要です。これらの犬種はもともと牧羊犬や狩猟犬として活躍してきたため、しっかりと運動の時間を確保しないとストレスを感じたり、問題行動の原因になったりすることもあります。
運動好きな飼い主であればこれらの犬種と一緒に散歩や運動を楽しむことができますが、時間や体力に自信がない場合は、チワワやマルチーズ、ポメラニアンなどの小型犬を選ぶと良いかもしれません。
いずれの場合も、散歩の頻度や時間が家族の日常生活に無理なく組み込めるかをしっかり確認し、継続できる運動習慣を作ることが大切です。
換毛期やにおいをチェック
換毛期やにおいの強さは犬種によって違いがあり、それぞれに適切なケアが重要です。
ダブルコート(上毛と下毛の二層構造)を持つ柴犬、ゴールデンレトリーバー、ミニチュアダックスフンドなどは、春と秋の年2回換毛期があり、大量の抜け毛が発生するため、飼い主には普段以上のこまめなブラッシングや部屋の掃除が求められます。ダブルコートの犬種は、被毛の奥に皮脂汚れがたまりやすく、シングルコートの犬種と比べてにおいが出やすい傾向があります。
一方、マルチーズのようなシングルコートの犬種は抜け毛が少ないため、お手入れが比較的簡単です。毎日忙しく、お手入れに多くの時間を取るのが難しい方は、シングルコートの犬種を検討しても良いかもしれません。
子犬を迎える準備
子犬を安心して迎えるためには、事前の準備が欠かせません。必要なグッズをそろえるだけでなく、子犬が安全に過ごせるように家の環境を整えることも大切です。ここでは、初めての飼い主さんでも迷わないよう、揃えておきたいアイテムと家の安全対策について詳しく解説します。
必要なグッズのチェックリスト
子犬の飼育を始めるにあたり、欠かせないグッズを事前に揃えておきましょう。
下記に、子犬を迎えるために必要なおもなグッズをチェックリストにまとめました。
・ケージ
・サークル
・トイレトレー
・ペットシート
・食器(フードボウル・ウォーターボウル)
・ブラッシング用品(ブラシ・コーム)
・デンタルケア用品
・爪切り
・シャンプー
・首輪・リード
・おもちゃ
おもちゃは誤飲を防ぐため、子犬専用の安全なものを選び、噛む力を養うために木のおもちゃを用意するのも良いでしょう。
家の安全対策と環境づくり
家の中には子犬にとって危険なものが多数あります。特に室内では、電気コードや薬品類、観葉植物など、子犬が誤って触れたり口に入れたりすると事故につながるアイテムが存在します。これらは子犬の手が届かない場所に収納し、誤飲やケガの防止に努めましょう。
家具の角や脚には、保護カバーや専用スプレーを活用することで、子犬のイタズラによる家財の破損やケガを防ぐことが大切です。滑りやすい室内の床には滑り止めマットを敷くことで、子犬の足腰への負担を軽減できます。
子犬の飼い方
子犬との暮らしが始まったら、毎日のお世話が本格的にスタートします。健康に育てるためには、食事の与え方やトイレトレーニング、室内環境の管理など、知っておきたいポイントがたくさんあります。ここでは、初めての飼い主さんが安心して子犬を育てられるよう、基本的なお世話の方法をわかりやすく解説します。
ごはんの与え方
子犬の食事は成長に合わせて餌の量や与える回数を調整することが大切です。生後間もない時期には、消化しやすい餌(フード)を使い、1日に3~5回に分けて与えることが推奨されます。
餌を急に変えると子犬の体に負担がかかるため、新しい餌や食材は少量ずつ、今までのフードに混ぜながら徐々に切り替えていく方法が望ましいでしょう。また、子犬が健康的に成長するためには、常に新鮮な飲み水を用意し、こまめな水分補給も忘れずに行ってください。
避けるべき食べ物
子犬に与えてはいけない食べ物は、健康被害を及ぼす可能性が高いため十分に注意が必要です。代表的なものには、ネギ類やチョコレート、アルコール、香辛料が挙げられます。
これらは中毒症状や消化器障害、アレルギーなどを引き起こしやすく、場合によっては命に関わるケースもあるため近づけないようにしましょう。
人間用の食品は塩分や脂質が多いため、子犬の健康に悪影響を与えることが多いです。おやつも犬用のものを使い、誤食が起きないよう常に管理すると安心です。
トイレトレーニングの進め方
トイレトレーニングは子犬との信頼関係を構築する第一歩です。排泄のリズムを把握し、決まった場所で行う習慣をつけることが大切です。
初めはペットシートやトイレトレーを利用し、成功した時には褒める声かけやおやつでポジティブに教えます。失敗しても叱らず、根気強く繰り返すことが重要です。
トイレは清潔に保ち、臭いがこもらないよう換気や掃除を心がけましょう。生活環境の変化に伴い調整が必要になることもあるため、柔軟に対応することが求められます。
温度・湿度の管理
子犬は体温調節がまだ未熟なため、温度と湿度の管理がとても重要です。
室内温度は25度前後を目安にし、特に夏場はエアコンの使用やカーテンで日陰を作るなどの対策を行いましょう。また、クールマットなどの冷却グッズも効果的です。
冬場に子犬を迎える場合は、エアコンを使用していても床付近が冷えやすいことに注意が必要です。あたたかい毛布やペットヒーターなどを利用して、寒さ対策をしっかりと行ってください。
湿度管理にも注意が必要で、40~60%程度を維持することが大切です。過度な乾燥や湿気は子犬の健康に悪影響を及ぼすため、加湿器や除湿機を状況に応じて使うと良いでしょう。
初めての散歩
散歩は子犬の社会性や運動能力の発達に役立つため、徐々に慣らしていくのが望ましいです。首輪やハーネスに馴染ませ、室内で着用の練習から始めると緊張が和らぎます。
初めての外出は短時間から開始し、静かな場所を選ぶことで不安を軽減します。子犬の歩調に合わせて無理なくゆっくり進み、楽しい経験を積むことが大切です。
適切なタイミングで排泄を促すことでトイレトレーニングもサポートできます。散歩後は脚を清潔にし、健康チェックを行う習慣を持つと良好な管理につながります。
かかりつけの動物病院
かかりつけの動物病院は、健康管理や緊急時の対応のために欠かせません。子犬が快適に受診できるよう、事前に施設やスタッフの対応を確認すると安心です。
健康診断や予防接種、避妊・去勢手術の相談も行い、適切なタイミングで施術を受ける体制を整えます。気になる症状や困りごとは早めに相談することが望まれます。日常的なケアのアドバイスや栄養指導も受けられるため、信頼できる獣医師との関係を築くことが重要です。
【月齢別】子犬の育て方
子犬の成長は早いため、その時期ごとに適切なケアを心がけることが大切です。発達段階に合わせて配慮しながら、安心して成長を見守ることが飼い主に求められます。
生後2ヶ月の子犬の育て方
ペットショップで子犬を迎える場合、生後2ヶ月ごろからのお迎えが一般的ですので、家に来たその日から丁寧なお世話を始めましょう。
新しく家に迎え入れたら、まず子犬が安心して過ごせるスペースを準備し、静かで落ち着いた空間を確保しましょう。家族みんなで優しく接し、子犬が家になじむためのサポートを心がけることも大切です。
食事については、これまで与えられていたものを基本にしつつ、消化の負担が少ないふやかしたフードを、1日に4~5回に分けて少量ずつ与えるのがポイントです。また、排泄の自己管理がまだできない時期なので、こまめにトイレに誘導し、徐々に家の中での排泄場所やタイミングを覚えさせましょう。
生後3ヶ月の子犬の育て方
生後3ヶ月の子犬は体力や好奇心が一段と増し、できることも少しずつ増えていきます。
特にしつけが重要で、たとえば、来客時には「ハウス」などの命令でクレートに入るようにしつけておくと、子犬自身も安心でき、飼い主にとってもトラブルを防ぐことができます。食事は成長に合わせて、栄養バランスの良いフードを1日3~4回程度を目安に与えましょう。
トイレトレーニングもこの時期に安定させ、トイレが成功した時はしっかり褒めて習慣化を促します。日常的なお手入れやケアもこの時期から習慣化すると、今後のお手入れがスムーズになります。
生後4ヶ月の子犬の育て方
生後4ヶ月の子犬は、より活発に動き回るため適度な運動が必要になります。散歩を始めるタイミングとしても適しており、環境に慣れさせながら楽しい時間を提供します。
食事は成長に合わせて徐々に固さを調整し、1日3回程度に減らす場合も多いです。トイレの成功率を高めるため、ルールを変えずに根気よく続けることが鍵となります。
この時期は基本的なコマンドの練習や問題行動の予防に取り組んでいきましょう。心と体のバランスに気を配り、安心できる環境の維持に努めることが必要です。
【犬種別】子犬の育て方
犬種によって性格や体の特徴が異なるため、子犬の育て方にも少しずつコツがあります。たとえば、活発で賢いトイプードル、警戒心が強めなチワワ、独立心のある柴犬など、それぞれに合ったしつけ方や接し方を知っておくことで、より良い関係が築けます。ここでは人気の犬種を中心に、子犬期の育て方のポイントを紹介します。
トイプードル
トイプードルは非常に頭が良く、しつけやすい犬種として知られています。賢いため、早い時期から基本的な指示に慣れさせることが効果的です。
毛が抜けにくいものの、定期的なトリミングやブラッシングが必要で、見た目の美しさを保つケアも欠かせません。活発で遊び好きなので、適度な運動を取り入れてストレスを溜めないようにすることが重要です。
また、飼い主とのコミュニケーションを好むため、一緒に過ごす時間を大切にすることで信頼関係が深まります。
チワワ
チワワは小型犬の中でも特に繊細な面があり、体調管理に注意が必要です。寒さに弱いため、室温や防寒対策に気を配ることがポイントとなります。
警戒心が強い性格を持つため、社会性を育てるために早いうちから人や環境へ慣らしていくことが大切です。吠え癖を防ぐためには、しつけを根気強く行い、安心感を持たせることが効果的です。
適度な運動と共に、無理のない範囲で遊びを楽しませることで精神的な安定を促せます。
柴犬
柴犬は独立心が強く、しっかりとしたしつけが不可欠な犬種です。運動量が多いため、毎日の散歩や遊びで体力を消費させることが健康維持に繋がります。
換毛期には大量の抜け毛があるので、こまめなブラッシングが必要です。
慎重な性格のため、社会性を養うために子犬のうちに様々な人や環境に慣らすことが重要です。適切な環境で安心感を持たせれば、忠実で家族思いのパートナーになります。
子犬のしつけの基本とコツ
子犬のしつけは、愛情と一貫性を持って接することが大切です。まずは、生活のルールを明確に決め、毎回同じ対応を繰り返すことで子犬に理解させやすくなります。
叱るときは感情的にならず、落ち着いた声で短く伝えることが効果的です。良い行動をした際には、その都度褒めたりおやつを与えたりして、ポジティブな反応を引き出す方法がしつけの基本となります。
また、複数のコマンドを一度に教えるよりは、一つずつ根気よく繰り返すことが成果を上げるポイントです。環境の変化やストレスがしつけに影響する場合もあるため、子犬の様子を注意深く観察しながら行いましょう。
社会性を育むために、他の犬や人との交流も積極的に取り入れると、安心して成長できます。しつけの進み具合には個体差がありますが、焦らず継続的に取り組むことが成功の秘訣です。
子犬を留守番させるときのポイント
子犬を留守番させるときは、留守中も安全で快適に過ごせる環境づくりが重要です。
まず、留守時に事故やケガにつながる危険な物は部屋から片付け、電気コードや薬品、誤飲の恐れがある小さな物は手の届かない場所に収納しておきます。
留守番させるスペースは、広すぎず子犬が安心できるケージやサークルがおすすめです。飽きないよう噛んでも安全なおもちゃを用意することで、留守中の不安や寂しさを和らげましょう。
また、長い時間の留守は子犬にとって大きなストレスとなるため、外出の時間はできるだけ短くし、帰宅したらたっぷり遊んで、しっかりコミュニケーションを取ってリフレッシュさせてあげてください。
子犬を飼う費用
子犬を飼い始めると、かわいさ以上に気になるのが「どれくらいお金がかかるのか」という点です。初期費用だけでなく、毎月のお世話にかかる出費も含めて、ある程度の予算を考えておくことが大切です。ここでは、子犬を迎えるときに必要な初期費用と、飼育にかかる継続的な費用について解説します。
お迎え時の初期費用
子犬を飼い始める際には、購入費や譲渡費用だけでなく、日々の生活に欠かせない基本的なグッズの購入費用も考慮する必要があります。初期費用は、購入費を除いてケージやトイレ用品、食器、首輪やリードなどで10~20万円程度です。
さらに、子犬の健康を守るために初回のワクチン接種や健康診断の費用もかかります。こうした費用はブリーダーやペットショップによってはセットになっている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
お世話にかかる費用
子犬のお世話にかかる平均的な年間費用は約34万円※で、主に食事代や日々のケア用品、医療費が中心です。毎日のフード代は成長に合わせて変わることが多く、質の良いものを選ぶことが健康維持に役立ちます。
医療費としては、ワクチンの追加接種や定期検診、予防薬代が継続的にかかります。急な病気やケガに備え、ペット保険の加入を検討しても良いでしょう。
子犬の飼い方に関するQ&A
子犬を飼い始めると、「室内と屋外どちらで飼えばいい?」「ワクチンはいつ打つの?」「避妊や去勢は必要?」など、たくさんの疑問が出てくるものです。ここでは、特に初めて犬を飼う方が気になりやすいポイントについて、よくある質問形式でわかりやすくお答えします。
子犬を飼うのは屋内?屋外?
犬はもともと群れで生活する動物であり、家族や飼い主と一緒に過ごすことが本来の自然な姿です。そのため、室内で飼うことが子犬にとって一番安心でき、幸せを感じやすいといわれています。
外で長時間過ごす場合、天候や温度変化の影響を受けたり、事故やストレス、見知らぬ人の通行などによる緊張が強まり、無駄吠えや物を壊すなどの問題行動につながるリスクも高まります。室内で生活することで、体調の変化や困っている様子にも飼い主がすぐに気づくことができ、健康管理もしやすくなるでしょう。
予防接種・ワクチン接種の時期は?
子犬の予防接種は、健康を守るうえで非常に大切なステップです。
子犬を迎え入れたら、まずは自治体への登録を済ませ、国で義務付けられている狂犬病の予防接種を行いましょう。狂犬病予防法により、生後3ヵ月以降のすべての犬にこの予防接種が必要です。集合接種のほか、動物病院でも受けることができますので、忘れずに手続きを進めましょう。
混合ワクチンは義務ではありませんが、複数の感染症を1本で予防できる大切なワクチンです。室内で犬を飼っている場合でも、人や物を介して病気が持ち込まれる場合があるため、積極的な接種が望まれます。
ワクチン接種の一般的なスケジュールは、生後6~8週目に1回目、生後12週目に2回目、生後16週目以降に3回目を接種することが推奨されています。さらに、その後は1年ごとに追加接種を行うことで、犬を感染症から守ることができます。
避妊・去勢手術の時期は?
一般的に避妊手術は生後5~6ヶ月頃の発情期が始まる時期に、去勢手術は性成熟期を迎える前の生後半年から1年未満に行われます。
ただし、犬種や個体差によって適切な時期が異なるため、必ず獣医師と相談しながら判断しましょう。早すぎる手術は骨や体の発達に影響を及ぼす場合があるため、慎重な検討が必要です。
マイクロチップは必要?
2022年6月から、ブリーダーやペットショップで販売される犬のマイクロチップ装着が法律で義務付けられました。そのため、ブリーダーやペットショップから受け取った犬には、すでにマイクロチップが装着されています。飼い主になった際には必ず登録情報の更新が必要です。
マイクロチップは登録された情報とマイクロチップのIDを照合することで、飼い主が正確に特定できる仕組みとなっており、万が一迷子になった時や、地震など災害時にも専用のリーダーで瞬時に個体識別ができます。
大切な家族である犬や猫の迷子予防や災害対策のため、飼い主にとってマイクロチップは有効で安心できる選択肢といえます。
まとめ│子犬の飼い方を理解して迎え入れよう!
子犬との暮らしは、毎日が新しい発見と喜びの連続です。しかし同時に、しつけやお世話、健康管理など、飼い主としての責任も伴います。
今回ご紹介したように、犬種選びから必要な準備、日々のケアまで、しっかりとした知識と心構えを持つことで、子犬も飼い主も安心して楽しい生活を送ることができます。
初めてのことばかりで戸惑うこともあるかもしれませんが、少しずつ経験を積んで、愛犬との絆を深めていきましょう。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、少額短期保険募集人の資格を保有。
豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら