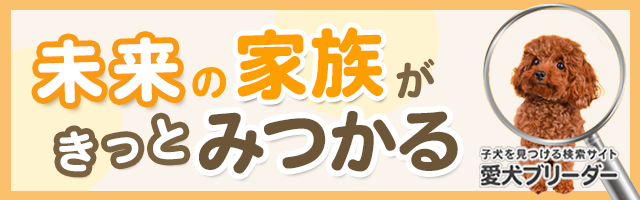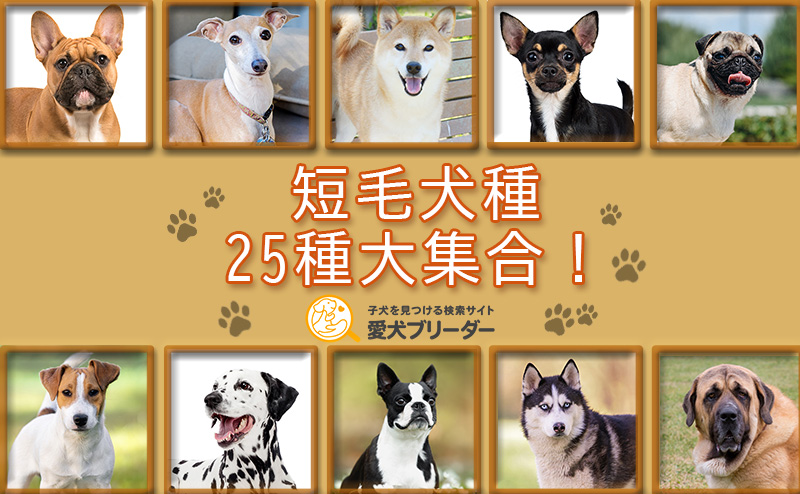犬の鳴き声一覧|鳴いてる理由は?愛犬の気持ちや健康状態を鳴き声から知ろう!
公開日:2025年4月1日
更新日:2025年5月22日

犬は言葉を話すことはできませんが、鳴き声を通して豊かな感情や気持ちを伝えています。
飼い主には、その鳴き声の意味や理由を正しく理解し、愛犬が伝えようとしている気持ちを汲み取ることが求められます。
この記事を読んで、愛犬とのコミュニケーションをより深いものにするヒントをみつけていきましょう。
鳴き声で知る愛犬の気持ち
犬の鳴き声は感情を表現するための重要な手段であり、愛犬が何を感じているのかを知る上でとても役立ちます。
愛犬がよく発する、代表的な鳴き声から紹介していきます。
喜びを伝えるトーン高めの「ワンワン」
楽しい時や嬉しい時によく聞かれるのが、高いトーンでの「ワンワン」という鳴き声です。
この「ワンワン」は、犬の気持ちの中でも特にポジティブな感情を伝える鳴き声の種類として知られています。飼い主が帰宅する際やお気に入りの遊びを始める時など、愛犬が喜びを全身で表現したい瞬間によく聞かれるものです。
しっぽを振りながら高めの声で鳴くときは心の底から嬉しいと感じていることが多いため、一緒に楽しむ気持ちで応えてあげましょう。
警戒心を示す低く太い「ワンワン」
低い声での「ワンワン」という鳴き声は、犬が警戒心を抱いた際に発する典型的な鳴き声です。
この鳴き声は、不審者や知らない人、または威圧感を感じる存在に反応して発せられることが多いです。犬がこうした警戒の理由で低く太い声を発する場合、その状況に対する防衛本能が強く働いていると考えられます。
愛犬が警戒心を示している際には、落ち着いて様子を見ると同時に、必要に応じて周囲の状況を確認し、愛犬にしっかりとしたサポートをしてあげることが大切です。
威嚇を表現する「ウーッ」「グルルル」
愛犬が低くうなる「ウーッ」や「グルルル」といった声は、威嚇の一環として考えられます。
このような鳴き声は、犬が自分の空間やテリトリーを守ろうとしているサインであり、テリトリーを侵害されそうになった時や食事中に近づかれた時、大事なおもちゃで夢中になって遊んでいる時にみられることがあります。
これらの表現には、自分の意思を相手に伝えようとしている心理が含まれることが多く、強い警戒心や相手に対する「怖い」という感情が反映されていることもあります。
このような状況では、無理に近寄ったり刺激する行動を避けることが大切です。
犬の威嚇のサインをしっかりと理解し、適切な対応を心掛けることが、愛犬との健全な関係を築く第一歩となります。
寂しさや甘えを示す「クンクン」「クーン」「ピーピー」
愛犬が鼻を鳴らして「クンクン」や「クーン」「ピーピー」と鳴くのは、多くの場合寂しさや甘えを表現しています。
例えば、飼い主が出かけてしまった時や自分を見てくれないときに発せられます。この鳴き声は単なる感情表現にとどまらず、食事や散歩など飼い主の行動を促す際にも使われます。
また、このような行動は飼い主との愛情や信頼関係を深めたいという気持ちの表れともいえます。「クンクン」や「クーン」という鳴き声が聞こえてきたら、寂しさがなくなるよう寄り添ってあげましょう。
痛みを訴える高い「キャン」
高い声で鳴く「キャン」という悲鳴には、痛みや驚きを伴う理由があると考えられます。
例えば、何かに挟まれてしまったり、突発的な痛みを感じた際にこのような声を出すことがあります。
このような鳴き声は単なる驚きだけに留まらず、身体に何らかの異常や違和感が生じている可能性を示している場合もあるため、注意深く観察することが重要です。
この鳴き方を何度も繰り返す場合は、早めに動物病院へ行き獣医師に相談することが大切です。
いつもと違う鳴き声に注意
愛犬が普段とは違う鳴き声を発する際、そこには何らかの変化や理由が隠されている可能性があります。
健康上の異常であったり、環境の変化によるストレスが考えられます。
特に、おとなしい性格の犬が急に吠えるようになった場合、その行動には犬の気持ちが反映されているかもしれません。
また、飼い主とのコミュニケーションが不足していることも鳴き声の変化につながることがあります。
愛犬の鳴き声が普段と違っていたら、その理由に注目し、適切な対応を心がけることが大切です。
犬も「ゴロゴロ」喉を鳴らす?
愛犬を撫でていると「ゴロゴロ」「グゥグゥ」といった声を出すことがありませんか?
唸った声とは異なり、どこから出る音なのか分かりづらいですが実は犬も猫と同じで喉を鳴らすことがあるようです。
主に「飼い主に愛情を伝えている」「リラックスしている」「お腹を空かせている」という意味があるんだとか。
日頃の愛情が伝わり安心や幸福を感じてくれていることが多いようなので、そんな時は、さらに愛を伝えてあげましょう。
喉ではなく鼻が鳴っている場合は呼吸器の不調の可能性もあるので、注意してください。
「要求吠え」って何?同じ鳴き声でもシチュエーションで意味が違う?
同じ鳴き声の場合でも、シチュエーションによっては異なる意味をもつことがあります。
例えば高い声で鳴く「キャンキャン」や、低めの声で鳴く「ワンワン」という声は、はやくご飯が食べたいときや、散歩や遊びを催促するときにも発せられる「要求吠え」の場合もあります。
愛犬の表情からも痛みを感じたり楽しい気持ちとは違うことが読み取れるでしょう。
要求鳴きや無駄吠えの対処法
犬の鳴き声はさまざまありますが、場合によってはすぐに反応するのではなく無視することが効果的な場面もあります。
「鳴けば思い通りになる」と覚えてしまうと問題になるでしょう。
対策としては、犬が吠えたときは冷静に反応をしないようにし、静かになったタイミングでしっかりと褒めてあげることが重要です。
こうすることで、「静かにしていると良いことがある」というメッセージが伝わります。
また、犬が吠えそうなときにテレビやラジオを流して気をそらせるのも効果的です。
要求鳴きに関しては、すぐに反応しないように心がけ、静かにしているときにのみ愛情を示すことで改善が期待できます。
まとめ|犬の鳴き声が示す感情と健康状態を理解しよう
犬の鳴き声は、飼い主にとって愛犬の気持ちを知るための重要なサインです。
鳴き声の種類やトーンを理解することで、その理由を把握し、愛犬の感情や健康状態をより適切に読み取ることができます。
愛犬と共に健やかで幸せな日々を送るためにも、鳴き声の種類を含めた日々のコミュニケーションに意識を向け、愛犬の気持ちを深く理解する姿勢を持つことが重要です。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、犬のしつけインストラクター、少額短期保険募集人の資格を保有。豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら
飼い方の関連記事
飼い方の記事一覧を見る人気の記事
新着記事