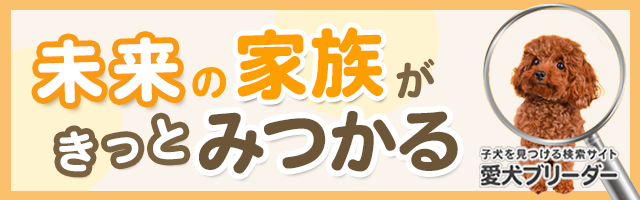犬が泣くのは悲しいから?涙の理由や感情、鳴き声の種類を解説
公開日:2025年3月31日
更新日:2025年5月22日

犬が「泣く」といっても、必ずしも悲しみが原因とは限りません。犬が涙を流して泣く場合、その背景には、病気や身体的な理由が関係していることもあります。感情面だけでなく健康面にも注意を払い、異常があれば獣医師に相談することが大切です。
犬は泣くのか?犬の感情について
犬は悲しい時に涙を流して泣くことはありませんが、さまざまな手段で感情を訴えています。
犬は言葉を持たないため、感情を表現する手段には限りがあります。その代わりに鳴き声や体の動き、さらには目の表情などを通して多様な感情を伝えます。たとえば、犬が嬉しいと感じた時や、悲しい・寂しいといった感情を抱えている時、それぞれ状況に応じて特有の鳴き声や仕草を見せることがあります。これらの行動には理由があり、そうしたサインを読み取ることで、飼い主は犬がなぜそのような行動をしているのかを理解できるようになります。
犬が何を感じているのかを察知するために重要なのは、日常の仕草や行動をよく観察することです。
例えば、犬が落ち着かない様子で部屋を行き来したり、周囲をきょろきょろと見回したりしている場合、それは不安やストレスを抱えている可能性があります。また、嬉しい時には、しっぽを振ったり飛び跳ねたりするなど、わかりやすい反応を示すことがあるでしょう。逆に、悲しい時にはしっぽを垂れる、元気がなくなるといった行動が見られることがあります。
犬の感情をより深く理解するためには、飼い主が犬の微妙なサインを見落とさずに気にかけることが大切です。犬がなぜそのような行動をするのか、その理由を探りつつ、適切に応えることは、結果的に飼い主と愛犬の信頼関係や絆を深める大きな助けとなるでしょう。
犬が悲しむときの仕草や鳴き声
犬が悲しんでいる時、特有の仕草や鳴き声が見られます。犬が示す悲しみのサインを理解することで、適切に寄り添い、安心させてあげることが大切です。
犬が悲しいときの仕草や行動
犬は悲しんでいるとき、食欲がなくなったり、しっぽをだらんと下げたりすることがあります。これらの行動は、悲しいという感情を持っている際に見られる自然な反応です。また、飼い主が名前を呼んでも声を発しない、あるいは鼻で小さく鳴く場合も、悲しさを表していることがあります。
犬は人間のように涙を流して泣くわけではありませんが、その行動や仕草から感情を読み取ることが重要です。
犬が悲しいときの声や鳴き方
悲しいときの犬の声には特別な特徴があります。愛犬の「クーン」というか細い鳴き声は、寂しさや悲しみを感じているときによく見られるものであり、犬が自分の気持ちを伝えるための方法の一つです。
犬は声のトーンや長さを変化させることで気持ちを表現します。例えば、「キャンキャン」と短く高い声を出した場合、怖い気持ちを抱いたり、パニックを起こしたりしている可能性があります。このような鳴き声を聞いたときは、抱っこしたり撫でたりするなど、犬に安心感を与える行動をとることで、その気持ちを和らげることができるでしょう。
犬が悲しむ理由とは?
犬が悲しいと感じる理由には、さまざまな要因が関係しています。犬の感情に深刻な影響を与えるきっかけを理解し、十分な配慮を行いましょう。
飼い主との別れや喪失感
犬は飼い主と密接な関係を築く生き物です。そのため、飼い主との別れや喪失感がもたらす影響は非常に大きいといえます。犬にとって飼い主は信頼のおける存在であり、日常生活の中心的な存在でもあるため、別れは特に悲しい体験となります。このような状況では、犬がその悲しみや喪失感に応じて行動や感情面でさまざまな変化を見せることがあります。
例えば、長い間一緒に暮らしていた他のペットが亡くなると、犬はその喪失を感受し深い悲しみに包まれることがあります。この悲しい気持ちは、食欲の減少や無気力といった形であらわれることがあります。また、環境の変化や心のストレスが理由で、鳴き声のトーンや頻度が変化することもあります。
こうした行動の変化は、愛犬の心の不調を示していることがあるため、飼い主としてしっかり観察する必要があります。特に飼い主と長く密接な関係を築いてきた犬ほど、別れに伴う影響は大きくなるため、注意深く愛犬の心身の健康を見守ることが大切です。
飼い主の感情に共感したとき
犬は共感力が高い動物であり、飼い主の感情を敏感に感じ取る能力を持っています。例えば、飼い主が悲しい気持ちでいると、その表情や仕草を読み取り、寄り添うような行動を示すことがよく見られます。
特に、飼い主がストレスや不安を抱えている場合、愛犬もその感情の影響を受けやすくなります。飼い主が悲しいと感じているときには、その気持ちが愛犬にも伝わり、一緒に心が沈むことがあります。
このような場合、飼い主が愛犬に十分な愛情を注ぎ、安心感を与えることがとても重要です。
飼い主に期待を裏切られたとき
犬は飼い主との生活の中で、様々な期待を持っています。例えば、毎日決まった時刻に散歩に連れて行ってもらえることや、一定の時間に食事を与えられることなどです。これらの期待が裏切られると、犬は大きな失望感を抱きやすくなります。特に、突然日常の習慣が変わると、その理由がわからない犬にとっては大きなストレスとなり、心の平穏を乱す要因となるのです。
飼い主が普段行っていた行動を突然変えると、愛犬は戸惑い不安を感じます。たとえば、散歩の時間が急に延びたり、食事が遅れたりした場合、犬は不安を抱え、悲しい気持ちになることが多いのです。このようなことが続くと、飼い主への信頼が低下し、ストレスがたまってしまう可能性もあります。
安定した生活や環境は犬の心と体に安心感を与えると同時に、飼い主との信頼関係を強化します。飼い主としての責任を意識し、犬にとってストレスの少ない生活を心がけましょう。
犬が涙を流す原因とは?
犬が涙を流している理由は、感情的なものではありません。犬が涙を流すのは、多くの場合、生理的な現象として起こりますが、病気の場合もあります。
感情ではなく生理現象としての涙
犬の涙は、身体的な理由によって分泌されることが一般的です。
これは主に生理的な反応として起こり、目がかゆくなったり、炎症を引き起こしたりした場合などに涙を流して対応する場合が多いです。この生理現象は、犬の体が不快感や痛みから自身を守るための自然な防御反応といえます。たとえば、目に異物が入った場合などに涙の分泌が増えることがあります。
愛犬が涙を流している場合、目に異物が入っていないか丁寧にチェックしたり、病気の兆候が隠れていないか細かく観察することが必要です。目やにが多くなったり、目が赤く腫れている場合には、速やかに獣医師に相談することをおすすめします。
涙が流れる病気の場合も
犬が涙を流す原因には、病気が絡むケースも少なくありません。たとえば、目の疾患やアレルギー反応が涙を引き起こす主要な要因となることがあります。涙の量が通常より多かったり、目が充血していたりする場合には、目の健康状態に何らかの異常がある可能性が考えられます。
涙が止まらず頻繁に流れる場合、結膜炎や角膜炎などの病気、犬の視力に影響を及ぼす深刻な病気の進行が原因になっている可能性も否定できません。こういった病気のサインは見逃さず、早い段階で動物病院を受診することが重要です。対処が遅れることで治療が難しくなるケースも考慮しなければなりません。愛犬の涙の状態や目の変化には敏感に気付き、健康を守るための適切な対応を心がけましょう。
犬が鳴く理由と対策方法
犬が鳴く理由は、その感情や状況に応じてさまざまです。一般的に、犬は注意を引きたいときや自分の感情を表現したいときに鳴くことが多く、警戒心から鳴く場合もよく見られます。犬が鳴く理由をしっかりと理解し、その感情を汲み取ることで、適切なしつけを行いましょう。
犬が鳴く理由の理解
犬が鳴く理由を理解するためには、その鳴き声の特徴や状況を注意深く観察することが重要です。犬が鳴くとき、その声の高さや質、頻度はもちろん、感情を表現している可能性も高いため、それを適切に読み取ることで、飼い主として愛犬の気持ちや意思を理解する手助けになります。
たとえば、高い声で鳴き尻尾を振る場合は、喜びや興奮といったポジティブな感情を表していることが一般的です。一方、低い声で鳴き続ける場合は、不安や警戒心といったネガティブな感情を含んでいる場合が多く、その鳴き方にも明確な意味があります。また、犬が玄関に近づく人に対して吠える場面では、周囲の安全を守ろうという警戒心がその行動の背景になっていることも考えられます。
犬が鳴く理由を正確に理解するためには、そのときの行動や周囲の状況も含めて観察することが重要です。これにより、犬がさまざまな場面でどのような感情を抱いているのか、それが何を意味しているのかを把握できるようになります。
鳴くときのしつけ方法
鳴くときのしつけは、犬の性格や環境にあわせて、適切なしつけを行うことが重要です。
まず、愛犬がどのようなタイミングで鳴くのか、その原因や状況を注意深く観察しましょう。たとえば、興奮や不安、注意を引きたいという気持ちが原因で鳴いている場合があります。こうした理由を理解したうえで適切な対応をすることで、効果的なしつけをすることが可能です。
最も基本的で効果的な方法の一つは、静かにしているときにしっかり褒めたり、ご褒美を与えたりすることです。これにより、静かにすることが良い行動であると犬に学ばせることができます。また、家族全員が一貫した対応を心がけることも重要で、異なる反応をすると犬が混乱してしまう可能性があります。
さらに、飼い主自身が冷静に行動することも効果的です。犬は飼い主の感情に敏感なため、落ち着いた態度を見せることで、犬も安心感を得られることがあります。もし、犬が周囲に不安を感じて鳴くことが多い場合には、安心できる環境づくりも必要です。安全な場所を用意したり、ストレスを軽減するための工夫を心がけましょう。
しつけには一貫性と時間が求められます。結果がすぐに出ない場合でも、焦らず根気よく続けることが大切です。
飼い主が無視するべきケース
犬が鳴いている時、すべての鳴き声に対して反応する必要はありません。特に、注意を引くために無駄に吠えている場合や、ただ退屈しているだけの場合には、飼い主が無視することが有効です。この対応は、犬に「鳴くことが無駄である」と理解させる手助けとなります。
ただし、飼い主が無視する際には注意が必要です。犬が鳴く理由が本当に必要なものである可能性も考えられるためです。したがって、まず鳴き声の背景や状況をよく観察し、その意味を理解することを優先しましょう。
子犬が鳴くときの対策方法
子犬が鳴く理由はさまざまですが、適切な対策で改善できることもあります。子犬の性格や好みに合わせた対策方法を見つけて、飼い主との信頼関係を築いていきましょう。
子犬のしつけの方法
しっかりとしたしつけは、子犬が鳴く問題を解決するために重要な役割を果たします。まずは子犬が鳴く理由を特定し、それに適切に対応することが必要です。
たとえば、空腹や不安感などが原因であれば、それぞれの状況に合った対応を心がけましょう。そして、子犬が静かにしているときには、すかさず褒めることで、静かにしていることが良い行動であると認識させることが効果的です。このようなしつけを通じて、子犬は正しい行動を学んでいきます。
さらに、子犬の鳴き声への対処では一貫性が重要です。要求に応じたり無視したりと対応が混在すると、子犬は混乱してしまい、望ましくない行動を強化してしまう可能性があります。そのため、ルールを明確にし、一貫した態度でしつけることが効果的です。
おもちゃを活用した対策
子犬はエネルギーが余りがちであるため、おもちゃを提供することで、ストレス発散や興奮を和らげ、無駄に鳴いてしまう状況を効果的に防ぐことができます。おもちゃの種類としては、ボールやロープといった動きのあるものや、知育玩具のような自ら考えるきっかけを与えるものが特におすすめです。
知育玩具は、問題解決を通じて脳を刺激するため、子犬が集中して遊ぶことができるほか、興奮状態を和らげる効果も期待できます。これにより、自然と無駄吠えが減少することもあるでしょう。また、それぞれの子犬に合わせた適切なおもちゃを選ぶことで、楽しみながら心身が満たされ、子犬のリラックスにもつながります。
このように「おもちゃ」を上手く活用することで、子犬が快適な環境で健康的に成長できるようサポートすることが重要です。
まとめ|犬が泣くのは病気のケースも
犬が泣くのは、感情的な要因と身体的な要因があります。寂しさやストレスで悲しげに鳴くこともあれば、目の病気や異常で涙を流すこともあります。
犬の仕草や鳴き声の変化を注意深く観察し、適切に対応することが大切です。感情的なサインを理解し寄り添うことで、愛犬との信頼関係が深まります。また、異常な涙が続く場合は健康面を考え、早めに獣医師に相談しましょう。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、少額短期保険募集人の資格を保有。
豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら