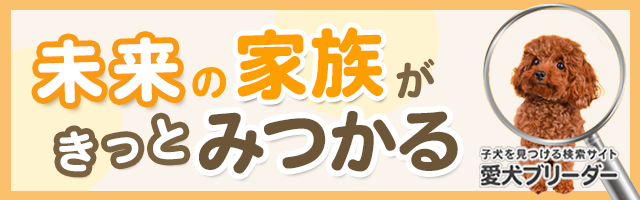犬の嫌いな匂いと体への影響は?避けるべき理由や好きな匂いについても解説
公開日:2025年3月27日
更新日:2025年5月22日

犬の嗅覚は非常に鋭敏であるため、私たちが普段心地よいと感じる匂いが、犬にとっては強い不快感やストレスの原因となることがあります。
愛犬の健康を守りながら快適な生活環境を整えるためには、匂いが犬に与える影響をしっかりと理解することが大切です。
日常的に使用するものや生活空間を見直し、犬が嫌う匂いを避けることで、ストレスのない環境を整えましょう。
犬が嫌いな匂い|体調不良や病気に繋がることも
犬が嫌う匂いには、化学物質や柑橘類、香辛料などが含まれます。
これらの匂いは犬に強い不快感を与え、場合によっては健康問題を引き起こす可能性があります。
「匂いを避ける」「鼻水や咳が出る」「元気がない」などの様子がみられる際は早めに原因を特定し、犬の近くではその物質を使わないなど配慮することが大切です。
【化学物質】
香水や洗剤、柔軟剤など化学物質を含む製品は犬にとって非常に苦手な匂いを発することが多いです。
これらの人工的かつ強い匂いは異臭と感じ、体調不良を引き起こす原因となることもあるため、犬から離れて使う必要があります。
【柑橘類】
オレンジやレモン、ライムなど、柑橘類の香りは多くの犬に不快感を与えます。
実よりも皮に含まれているリモネンという成分が強い刺激やにおいを持ち、特に猫にとっては有毒だとされています。
柑橘類の匂いはしつけの一環として使われることもありますが、犬の反応に注意を払い、無理に近づけることのないよう心掛ける必要があります。
【香辛料】
コショウや唐辛子、わさび、からしといった香辛料は犬に不快感を与えるだけでなく、少量でも誤って摂取すると下痢や嘔吐のトラブルを引き起こすことがあります。
犬が近くにいる場所で料理や食事をする際には十分注意する必要があります。
【酢】
酢の匂いは犬にとって非常に嫌なものとされています。
初めは嫌がってもその後慣れてしまうこともあるようですが、犬の敏感な嗅覚にとって強い刺激となるため注意してください。
【アルコール】
犬の体はアルコールを正しく分解できないため、誤って摂取すると中毒症状を引き起こすことがあります。
匂いを嗅ぐだけでも害があるといわれています。
消毒剤にも反応することがあるので、アルコールが含まれる製品や飲み物の近くには愛犬を近づけないよう心掛けることが大切です。
【タバコ】
タバコの臭いや煙はストレスの原因となるだけでなく、誤って食べてしまった場合は命にかかわります。
また、煙を吸い込むことで受動喫煙となり悪影響を及ぼし、アレルギー性鼻炎を引き起こす原因にもなることがあります。
タバコの置き場所、喫煙場所、吸い殻の処理は犬が届かない位置で行うなど、十分に注意してください。
【ハッカ(湿布)】
ハッカは強い清涼感と香りを持つため、犬にとっては苦手な存在です。
湿布やクリームに使用されることが多いですが、強い香りはストレスや不快感を与える可能性があるため、取り扱いに注意が必要です。
犬が触れる場所には置かないよう心掛けましょう。
【マニキュア】
マニキュア特有の強い化学的な香りは、嗅覚の不快感だけでなく、犬の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
マニキュアを使用する際は、犬がいない別の部屋で行うことが望ましいでしょう。
使用後は部屋の換気を十分に行い、愛犬への影響を減らすよう心掛けてください。
【コーヒー】
コーヒーは犬にとって好まれない匂いとされることが多いです。
コーヒーや緑茶に含まれる「カフェイン」の分解ができないため、少量であっても体に影響を及ぼす可能性があります。
誤飲には注意し、犬の届かないところに置くようにしてください。
犬への負担を減らす匂いの選び方
大切な愛犬の健康を保つためには、できる最大限の配慮をし負担を軽減する意識をもちましょう。
ここでは匂いの選び方で特に注意すべき点を紹介します。
アロマ
犬のアロマテラピーが注目を集めていますが、一部のアロマオイルは犬にとって危険であるため注意が必要です。
たとえば、ペパーミントやユーカリは消化不良や嘔吐、呼吸困難や神経に対する影響を引き起こす可能性があります。
そのほかの「安全」といわれるアロマでも、必ず低濃度のものを使用することが重要です。
アロマは、基本的にアルコールや植物油などで希釈されたもので「犬はアルコールを分解できない」ということを忘れないようにしましょう。
香水
香水は人工的につくられた香料のため、犬にとって極めて苦手な匂いです。
多く吸い込んでしまったり、少量でも日常的に吸収してしまう場合は体内で処理できず蓄積され、体調不良を引き起こすこともあります。
香水を使う場合は量に気を付け、犬がいる空間では使用を避けるよう心掛けるべきです。
消臭剤や芳香剤
消臭剤や芳香剤も犬にとってはストレスの原因となります。
また、香水と同じで日常的に吸収してしまう場合は体内で処理できない場合がありますので注意が必要です。
重曹やハーブなどの天然成分を基にした消臭剤を選ぶと犬への影響は減らせると考えられています。
「ペットにやさしい」ペット用の消臭剤も販売されていますので調べてみましょう。
犬の嗅覚は人間の何倍なの?
犬の嗅覚は、匂いによっては20km先でも嗅ぎ分けることができ、重要な情報を収集したり、コミュニケーションを取ったりするための役割を果たしています。
また、犬の嗅覚は「人間の100万倍以上」といわれる驚異的な能力を持っています。
ただしこの数字は、犬が匂いを100万倍強く感じているというわけではありません。
人間がかろうじて感じることのできる匂いの強さを「1」とした場合、犬はその100万分の1に薄まっても嗅ぎ取れるという意味で「100万倍」と表現されています。
また、匂いによって反応する強さは異なり、例えば、人間の足の裏の匂いの元となる吉草酸(きっそうさん)には100万倍以上の敏感さを示し、汗の悪臭である酸臭に対しては、最大1億倍の感度があるとも言われています。
犬が好きな匂い3選
犬は特定の匂いに対して驚くほどの魅力を感じることがあります。
このような犬にとって心地よい要素を理解することで、愛犬とのコミュニケーションをより深め、安心感を与える環境を作ることができるでしょう。
ここでは、「犬の好きな匂い」を3つご紹介します。
①飼い主の匂い
犬にとって飼い主の匂いは安心感をもたらし、飼い主の愛情を強く感じることができます。
「愛犬が家族の匂いがする衣類や寝具の上で寝ていた」という話を聞いたことがあると思います。
そのため、動物病院やペットホテルに連れて行く際には、飼い主の匂いがついた物を一緒に持参すると、犬は安心することができます。
また、人間の身体から発せられる特有の匂い、時には傷口などから出る微弱な血の匂いも、犬が飼い主を見分けるためのヒントとなる場合があります。
②タンパク質の匂い
タンパク質に関連する匂いは、犬が非常に好む特徴の一つとして挙げられます。
肉や魚などの食材から発せられる匂いに加え、血の匂いも犬にとって本能的な魅力を持つ要素です。
特に運動後や散歩の後にタンパク質を含むおやつを与えると、犬はその香りに強く惹かれ、喜ぶ姿を見せることが多いです。
このため、食事の準備やおやつの選び方において、犬の好みや本能を考慮したタンパク質や血の匂いが感じられる食材を選ぶことが重要です。
③ミミズ
「犬が干からびたミミズに体をこすり付けている」という話を聞いたことがありませんか?
犬が好む匂いの中には、少々意外なものもあり、そのひとつがミミズの匂いです。
特に子犬は初めて見るものや匂いに対して好奇心旺盛であり、土の中にいるミミズに興味を示して匂いを嗅ぐことがあります。
これは、犬が自然の中で感じる本能的な行動の一部であり、草むらや公園などで見られる典型的な行動といえるでしょう。
この匂いへの興味は、子犬だけでなく成犬においても狩猟本能や探索本能を刺激する一因となることから、多くの犬が同様の行動を見せることがあります。
④お尻の匂い
犬のお尻の匂いは、他の犬とコミュニケーションを取るための重要な方法でもあります。
犬同士が嗅ぎ合う行動は、相手の健康状態や状態を知るための一助とされています。
これにより、犬は仲間との関係を深めたり、社会的なヒエラルキーを理解したりすることが可能になります。
この匂いの重要性は、人間には理解しがたいものですが、犬にとっては非常に大切なコミュニケーションの一環だと言えるでしょう。
まとめ
犬の嫌いな匂いや苦手な匂い、好きな匂いについて解説しました。
嗅覚が優れた犬にとって、嫌いな匂いはストレスを与えるだけでなく健康にも影響するため、刺激の強い匂いや人工的なものには注意し、少しでも気になったら調べて理解することが大切です。
愛犬が安心する人工的なものを使用しない「飼い主さん自身や家族の匂い」でいっぱいな環境で、穏やかな毎日を過ごしましょう。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、少額短期保険募集人の資格を保有。
豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら