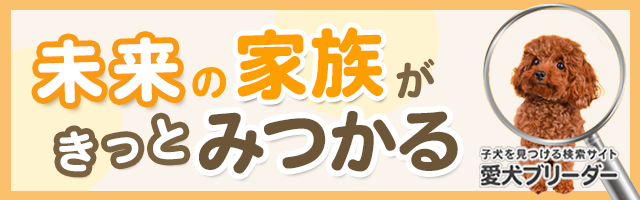子犬の散歩はいつから?散歩を始める時期・練習方法・注意点をご紹介
公開日:2025年3月21日
更新日:2025年5月22日

子犬を迎えたばかりの飼い主なら、早く一緒に散歩したい!とワクワクしていることでしょう。でも同時に、「いつから外に出していいの?」「何か準備は必要?」と不安を感じることもあるかもしれません。
実は、子犬の散歩はただの運動ではなく、大切な社会化の第一歩でもあります。適切なタイミングで始めることで、犬の性格形成にも大きく影響を与えるとされています。
そこで本記事では、子犬の散歩デビューの時期や練習方法、注意点を詳しく解説します。愛犬と安心して散歩を楽しめるよう、ぜひ最後までチェックしてください!
[目次]
子犬の散歩が必要な理由って?
まだ体が小さいため、外に連れ出すと危ないと考えている飼い主もいるかもしれません。
そこでまずは、子犬の時期に連れ出して散歩が必要なのか、散歩によってどんなメリットがあるのか解説をしていきます。
飼い主との上下関係をはっきりさせて信頼関係を築くため
散歩は、単なる運動ではなく、飼い主との信頼関係を築く大切な時間です。子犬は好奇心旺盛で自由に動きたがりますが、飼い主が散歩の主導権を握ることで、自然と上下関係が明確になり、安心感を持つようになります。
毎日の散歩やコミュニケーションを通じて、「飼い主は頼れる存在だ」と感じてもらうことが信頼関係を深める第一歩。小さな積み重ねが、愛犬との絆を強くしていきます。
大切なのは、散歩を楽しみながらも、飼い主が優しくリードし、愛情を持って接すること。そうすることで、愛犬との関係はより良いものになっていきます。
信頼関係が確立されると、子犬は飼い主の指示に従いやすくなるため、しつけにも良い影響を与えるでしょう。
子犬の社会性を育むため
子犬の社会性は、生後3〜6ヶ月の「社会化期」が鍵とされます。
この時期にさまざまな人や犬と触れ合い、外の環境に慣れることで、将来どんな場所でも落ち着いて過ごせる犬に育ちます。そのためには、散歩を活用して積極的に外の世界を体験させることが大切です。
たとえば、公園で他の犬と遊ばせたり、街中で車や自転車の音に慣れさせたり。違う地面を歩かせるだけでも、子犬にとっては新鮮な学びになることでしょう。「怖いものではない」と理解することで、不安や警戒心が薄れ、落ち着いた性格に成長していくのです。
運動によって健康を維持するため
子犬の成長期には、適度な運動で筋肉を鍛えることがとても重要です。
散歩によって食欲が促進されたり、ホルモンバランスが整ったりすることもあり、ただの散歩と侮ってはいけません。
室内で走り回るのとは違い、外を歩くことでさまざまな地面の感触を学び、脳の発達を助ける効果も期待できます。
また、外の刺激に触れることでストレスが軽減され、落ち着いた性格に育ちやすくなるのも大きなメリットです。
鳥のさえずり、風のにおい、季節の変化を感じながら歩く時間は、飼い主だけでなく愛犬にとっても心の健康を育む大切な時間になることでしょう。
子犬の散歩を始める時期の目安
「子犬の散歩、いつから始めるべきか?」と悩んでいる飼い主の方も多いのではないでしょうか。子犬にとって散歩は、ただの運動の一環ではなく、社会性を育む大切なステップでもあります。では、そのデビューはいつが適切なのでしょうか?適切なタイミングで散歩を始めるために、具体的な時期をご紹介します。
2~3回目の接種が終わってから2週間後
ワクチン接種後の2週間は、免疫が完全に整うための大切な時間です。
この2週間は、子犬の体調をしっかり観察し、無理せず少しずつ外の世界に慣れさせる期間です。散歩デビューに向けて、初めから長時間の散歩をするのは避けましょう。
まだ免疫力が十分でない可能性もあるため、まずは短時間の散歩や抱っこ散歩を通じて、外の環境に少しずつ慣れさせていくことが大切です。
子犬の健康と安全を最優先に考えると、焦らずに慎重に進めることが、愛犬の未来にとって大事です。ワクチン接種後の2週間が過ぎ、体調に問題がないことを確認した上で、散歩デビューを迎えてください。
生後3~4ヶ月を過ぎた時期
生後3〜4ヶ月は、子犬にとって散歩を始める絶好の時期とされています。ワクチン接種が完了し、免疫力が安定してきているため、安全に外に出られます。また、社会化期にあたるため、さまざまな刺激を受けて成長できる時期でもあります。
音や匂い、風景など新しい体験が、子犬の性格形成に影響を与えますが、初めての散歩は静かな場所で短時間から始め、徐々に慣れさせていくことが大切です。
子犬が好奇心旺盛でたくさん遊びたがっても、生後間もないため無理は禁物です。少しづつ散歩の時間を増やしていくように心がけてください。
個体差があるので獣医師と相談する
子犬によって体調や成長度合いは異なります。散歩デビューのタイミングについては一概には言えないため、慎重に判断しましょう。
特に散歩を始めることで、外の世界に触れたり過剰なストレスを感じたりすることもあります。また、ケガのリスクもあるため、自己判断は避けるべきです。
素人では判断が難しい部分も多いため、専門知識を持つ獣医師に相談することが大切です。子犬の健康状態や性格を考慮して、散歩の時期を提案してくれるでしょう。
散歩デビュー前に必要な準備や練習方法
散歩デビューを控えた子犬のための、必要な準備や練習についてご紹介します。
飼い主としても、初めての散歩になりますので、しっかり準備をしてデビューを飾りましょう。
リードや首輪に慣れさせる
子犬が散歩を始める前に、首輪とリードに慣れさせることが大切ですが、市販品ならどれでも良いわけではありません。
子犬に合ったサイズの首輪を選ぶようにしてください。サイズが大きいと散歩中に首輪が抜けたり、小さいと息苦しくなってしまう可能性があります。
リードも適切な長さと強度を選ばなければ、ちぎれたり、犬が遠くに離れてしまったりしますので、周りに迷惑をかけてしまうことがあるでしょう。
室内であらかじめ首輪やリードを装着する練習をしておけば、子犬の不安を和らげられます。日常的に装着を行うことで、散歩時のストレスを軽減し、安心して歩くことにもつながります。
散歩グッズの準備をする
散歩デビューに向けて、子犬のための準備が重要です。リードと首輪以外にも、必要なアイテムは意外とたくさんあります。
- うんち袋
- 水
- おやつ
- おもちゃ
- ペット用の迷子札
うんち袋は散歩中のマナーとして欠かせません。排泄物は放置せずきちんと回収して、環境美化への配慮を忘れないようにしましょう。
散歩中は子犬も飼い主も水分補給が欠かせません。夏の暑い日はもちろんですが、冬も常に補給できる方が安心です。脱水症状を防ぐためにも忘れないようにしましょう。
良い行動を促すためにおやつを用意するのも効果的です。行動に対してポジティブな認識をさせられます。おもちゃがあれば、楽しく遊びながら運動量を増やせるため、近場の散歩でも十分な効果が期待できます。
もしものときを考えて、迷子札も身に着けましょう。散歩に慣れてきても、見知らぬ場所に迷い込みパニックになるかもしれません。
室内で散歩の練習を行う
首輪やリードの装着に慣れたら、室内で散歩の練習を始めましょう。最初はリードを軽く持ち、ゆっくりとしたペースで歩く練習をします。子犬がまだ不安定なうちは、無理をせず、少しずつ状況に慣れさせることが大切です。
練習中、子犬が反対方向に引っ張ったり、思うように歩かなかったりすることがあるかもしれません。
その状況でも焦らず根気よく続けていくことで、少しずつ理解が深まります。
おやつをうまく使って、ポジティブな強化を行うことも効果的です。
室内での練習は、散歩デビューへ向けた大事なステップです。子犬が自信を持って歩けるようになると、外での散歩もより楽しい体験になるため、できるだけ時間をかけて行うようにしましょう。
屋外の音やニオイなど刺激に慣れさせる
子犬が外で散歩を始めるまでに、屋外の音やニオイなどの刺激にある程度慣れてもらう必要があります。
特に、初めての音やニオイは子犬にとって驚きや不安を引き起こす可能性があります。
音やニオイなどの外的刺激に対しては、散歩デビュー前に慣れておくのがおすすめです。
散歩に対する抵抗感や苦手意識を軽減でき、スムーズな散歩スタートの一助になることでしょう。
ご家庭でもできるやり方として、庭やバルコニーなどを使って、外の環境に少しずつ触れさせることから始めましょう。
風の音、車の騒音、人の話し声などに対する反応を観察し、リラックスさせる声かけやふれあいが大切です。
外で遊ぶ他の犬や人の存在にも慣れさせることで、社会性も育まれます。慣れの段階を挟むことで、スムーズな散歩デビューが可能となります。
家族以外の人と触れ合って慣れさせる
子犬は家族以外の人に対して不安を感じることがあります。特に初対面の人と接触する際、これまでの経験から恐れやパニックを引き起こすことも少なくありません。散歩では多くの見知らぬ人と出会うため、その場面に慣れさせることが重要です。
信頼できる友人や親戚を通じて、少しずつ家族以外の人と触れ合いの機会を持つことで、子犬の恐怖感を和らげることができます。このような社会化経験が、散歩中のスムーズな行動に繋がるでしょう。定期的に多様な人々と交流させることで、子犬の社会性が育まれ、散歩を楽しむための基盤が築かれます。
初めて散歩をするときの注意点
初めての散歩をするときは、飼い主側も注意すべきことがいくつかあります。大切なのは、最初から無理をせずに徐々に散歩の距離や時間を増やしていくことです。
ワンちゃんの様子をよく観察しながら、その子に合ったペースで散歩をさせてあげましょう。
短時間・短距離から始める
散歩デビューからしばらくは、ストレスを避けるため、短時間で短距離から始めるのがおすすめです。
歩き慣れていない環境だと体に負担がかかる可能性もあるため、徐々に距離や時間を延ばしていくようにしましょう。
また最初のうちは散歩コースを固定して、ある程度散歩そのものに慣れてもらうことも大切です。最初から毎回ルートを変えていると刺激が多すぎて、逆にストレスや疲れが溜まるかもしれません。
慣れてきたら、徐々にいろんなルートを開拓して散歩の楽しさを味わいましょう。
散歩中の子犬の様子をよく観察する
散歩中は変わった様子がないか、子犬をよく観察しましょう。子犬目線と人間目線は違うため、飼い主が気付かないような何かが起こるかもしれません。
子犬の様子に意識を向けておくことで、何があっても早めに気づいて対処できます。
慣れるまでは抱っこ散歩も取り入れる
慣れる時間を作っていても、外の世界を怖がる様子を見せることは十分考えられます。あるいは、初めて見るアスファルトの上を歩きたがらないかもしれません。
その場合は無理に歩かせようとせず、抱っこをしながら、外を歩くだけでも十分です。外の世界に触れる時間を増やして、興味を持ってもらいながら、外の世界への抵抗感を徐々に克服してもらいましょう。
夏場や冬場は子犬の体調対策を十分行う
気温が極端になる夏場と冬場は、体調管理をしっかり行うようにしましょう。
特に夏場の散歩は注意が必要です。ペットは人間よりも地面に近いため、夏場の焼けるような日差しを直接受けます。猛暑日は地面付近の温度が50度を超えることも多く、やけどや熱中症、脱水症状の危険が高まります。
夏場は、日中を避けて早朝や夕暮れに行ったり、屋内のドッグランの利用を増やしたり、暑さを避けてください。
冬場の寒さは軽く考えがちですが、小型犬や短毛種の子犬は防寒着を着せるなどの寒さ対策も必要です。また、路面凍結によるスリップで思わぬけがをすることも想定して、コースの状況を確認しながら散歩をしましょう。
拾い食いや危険物に触れないよう気をつける
子犬は好奇心旺盛な傾向にあるため、落ちているものを口に入れてしまうこともあります。そのほか、除草剤などの薬品がかかった草や毒性を持った植物など、落ちているもの以外にも危険は潜んでいます。
おなかを壊したり、感染症のリスクが高まるため、拾い食いには十分注意して見守りましょう。
歩かないときは無理をさせない
散歩に出かけても歩こうとしなかったり、立ち止まって言うことを聞いてくれなかったりするときもあるでしょう。
その場合は、無理やり散歩に連れ出したり、引っ張るようなことをすると、散歩嫌いになる可能性があります。
まずは短距離・短時間から始めて、徐々に散歩の時間や距離を伸ばしていくのが良いでしょう。
散歩の途中で怖がったり、立ち止まってしまうなら、人や車の行き来が少ない公園などの場所から、始めるのもおすすめです。
子犬の時期は散歩後のケアも大事!
愛犬の散歩デビューも無事終わりほっと一安心したいところですが、散歩後のケアも忘れずに行ってあげましょう。
散歩中気づかなくても、好奇心から様々なものに触れているかもしれません。
それらの汚れや細菌を取り除き、体に異常がないか確認することで、今後も安全に楽しく散歩ができるでしょう。
足を洗浄して身体ブラッシングする
体に付着したごみやほこりを落とすためのブラッシングはもちろんですが、肉球に付着したごみなども綺麗に取り除き、清潔な水で洗ってあげましょう。その際に、肉球や皮膚など足に問題がないかチェックしてあげてください。
肉球はとても敏感です。特に冬場は路面の雪や氷、融雪剤でダメージを受けやすくなります。散歩デビュー直後だけでなく、帰宅後は毎回のルーティーンとしてチェックとブラッシングをしてあげましょう。
水分補給と体調観察を行う
散歩の後は、水分補給の時間を作ってあげましょう。
熱中症や脱水症状になりやすい気温が高い日はもちろんですが、気温が高くない日でも、運動量が多い日やたくさん遊んだ後は、思いがけず汗をかいていることもあります。
運動後のリラックスタイムを作る
外の環境に触れることで、気分が高揚している状態が続いている可能性があります。家に帰った後は、子犬がリラックスできる環境を整えて、休ませてあげましょう。
またお気に入りの場所や好きなおもちゃをそばにおいてあげるなど、普段の居心地の良い環境に戻して、運動後のリラックスタイムを意図的に作るようにしてください。
子犬の散歩の頻度と時間も確認する
成長過程となる子犬時期は、大切な時期となります。子犬のときと成犬のときで散歩の時間や距離は変わります。子犬の時期の散歩は単なる運動だけではなく、社会性を育む側面もあります。
一般的に、小型犬と中型犬は生後12か月くらいまでが成長期とされますが、犬種や個体によって異なります。大型犬はより成長期が長くなるため、獣医師と相談しながら子犬時期の運動量や散歩頻度を決めるのが良いでしょう。
愛犬に合わせて少しづつ楽しい散歩を
愛犬との散歩は何にも代えられない至福の時間です。何にでも興味を示す子犬特有の可愛らしさは、わずかな期間しか経験できません。
正しい散歩を通じて社会性を育み、子犬の成長を見守ってあげましょう。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、少額短期保険募集人の資格を保有。
豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら