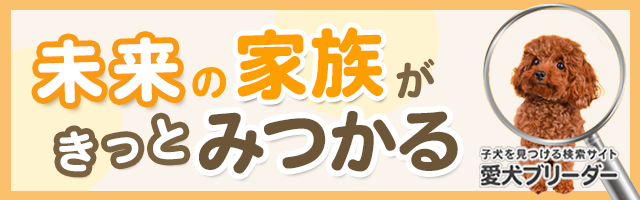ビーグルの平均寿命はどのくらい?ギネス記録はある?かかりやすい病気についても解説!
公開日:2025年5月9日
更新日:2025年5月23日

ビーグルは愛らしい見た目と活発な性格で人気のある犬種です。どれくらい長く一緒に過ごせるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事ではビーグルの寿命だけでなく、かかりやすいとされている病気や長生きのためのポイントもご紹介します。
ビーグルの寿命
それでは、寿命は何年くらいなのか早速見ていきましょう。
ビーグルの平均寿命
ビーグルの平均寿命は一般的に12〜15歳程度とされています。これは中型犬の中でも標準的な範囲の寿命です。
遺伝的に大きな先天的疾患が少ないため、健康的な生活を送れば比較的長生きしやすい犬種と言われています。
ただし、生活環境や健康管理の状態、日々の運動量や食事内容、ストレス管理などによって寿命が大きく左右されることもあるため注意が必要です。
ビーグルの最高寿命
ビーグルの最高齢について、残念ながら公式なギネス世界記録は存在しませんが、なんとアメリカ・バージニア州のビーグル「ブッチ(Butch)」が28歳まで生きたとされてる情報があります。
ビーグルの平均寿命から考えると、これは非常に珍しい長寿と言えるでしょう。
人間に換算すると何歳になるか
犬の年齢を人間の年齢に換算する方法には諸説ありますが、一般的には犬が1歳のとき、人間に換算すると約12歳に相当すると言われています。
2歳までは急速に成長し、2歳になると人間の25歳程度に相当します。そこから先は1年ごとに約4歳ずつ歳を重ねる計算がよく用いられています。
これをビーグルの平均寿命である12〜15歳に当てはめてみると、人間でいう約68〜81歳までに該当します。愛犬の健康を守るためにも、この換算を参考にしながら日々の生活やケアの質を高めていきましょう。
ビーグルがかかりやすい病気
ビーグルは特有の病気にかかりやすい傾向もあります。ここでは7つの病気について解説します。
①椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアは、背骨と背骨の間にある「椎間板」というクッションの役割をする組織が飛び出したり変形したりして、近くの神経を圧迫してしまう病気です。
ビーグルのような活発な犬種はジャンプや走り回ることが多いため、椎間板に負担がかかりやすい傾向があります。
初期段階では、痛みを感じて抱っこされるのを嫌がったり、段差を拒否するなど行動に変化が現れます。さらに症状が進行すると、足の動きが鈍くなったり歩行にふらつきが出るなど、日常生活にも支障が出てくることがあります。
そのため、椎間板ヘルニアは早期発見が非常に重要です。
治療法には主に薬物療法が用いられ、状態が重い場合は手術が選択されることもあります。
犬に激しい運動をさせないことや、肥満を予防することが椎間板ヘルニアの発症リスク軽減に繋がります。
②外耳炎
外耳炎は、耳の外側から耳道にかけて炎症が起き、赤みやかゆみ、痛みなどの症状が現れます。
ビーグルのような垂れ耳の犬種は耳の中に湿気がこもりやすく、細菌や真菌が繁殖しやすい傾向があります。そのため、湿気が溜まりやすい耳は定期的な掃除とケアが必要不可欠です。
外耳炎を放置すると、中耳炎など重篤な耳の病気へ進行する恐れがあるため、異変を感じた場合は早めに動物病院で診察を受け、獣医師の指示に従って適切な治療薬を使用することが大切です。
普段から耳の中を清潔に保ち、耳の状態をこまめにチェックする習慣が外耳炎の予防にも繋がります。
③糖尿病
糖尿病は、体内でインスリンの働きがうまくいかず、血糖値が高くなる病気です。
ビーグルは食欲旺盛で肥満になりやすく、他の犬種と比較しても糖尿病の発症リスクが高い傾向があると言われています。
主な症状としては、多飲多尿、食べているのに体重が減るなどが見られることが多いです。
これらの変化に気付いたら早めに動物病院で診てもらう必要があります。
治療にはインスリン注射や食事管理が中心となり、日々のカロリーコントロールが予防には欠かせません。
④白内障
白内障は、目の水晶体が徐々に白く濁ることで視力が低下し、進行すると失明に至ることもある病気です。近年、犬の平均寿命が延びたことで高齢犬に多く見られる疾患となっています。
初期症状としては、目が白っぽく見えたり、以前より物にぶつかりやすくなるなど行動の変化が見られます。
治療には点眼薬による進行抑制と、人工レンズの挿入手術による視力回復があります。
白内障の原因とされる活性酸素は、紫外線を過剰に浴びることで体内に増加すると言われています。予防として散歩の時間帯を工夫してあげるのも良いでしょう。
⑤てんかん
てんかんは、脳の異常な興奮によって発作が起こる病気です。
発作は突然犬に現れ、体が硬直したり痙攣したり、失神のような状態になる場合があります。特にビーグルは遺伝的にてんかんを発症しやすい犬種として知られていますが、発作の頻度や症状の重さは個体差があるため、日頃から飼い主が注意深く観察することが重要です。
治療には抗てんかん薬が用いられ、発作の原因や頻度をコントロールすることで犬の日常生活の質を維持できます。
てんかんの症状を持つ子には、定期的な動物病院での診察や継続的な健康管理が健康維持の重要なポイントとなります。
⑥クッシング症候群
クッシング症候群は、副腎皮質ホルモンの過剰分泌によって引き起こされる病気です。
主な症状としては多飲多尿、食欲増進、体重増加がみられ、さらに皮膚が薄くなったり、毛が抜けやすくなるといった特徴があります。症状が進行すると筋力低下や免疫力の低下などの健康問題につながる場合があるため、定期的な健康診断で早期発見を目指しましょう。
検査で早期にクッシング症候群が見つかれば、適切な治療により症状のコントロールが可能です。
わずかな異変でも、気付いた際には速やかに獣医師へ相談しましょう。
⑦甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンが不足することで新陳代謝が低下し、健康に様々な影響を及ぼす疾患です。
ビーグルにおいても発症例が多く見られ、シニア期で診断されることが多い特徴があります。
主な症状としては、元気がなくなる、体重が平均より増加する、毛が抜けやすくなる、皮膚のかゆみや被毛の質の低下などが挙げられます。
体温が下がる傾向も見られ、日常的な行動の変化が見逃されやすいため注意が必要です。
これらの症状ははっきりと現れないこともあるため、定期的な健康診断や血液検査によって早期に発見することが推奨されます。
ビーグルの健康寿命を延ばすためのポイント
ビーグルの健康寿命を延ばすためには日々のケアがとても重要です。ここでは、長く健康に過ごすために大切な5つのポイントを紹介します。
①食事の管理
ビーグルは食欲の旺盛さから肥満になりやすいとされているため、食事の管理がとても重要です。
より長く健やかに過ごしてもらうためには、年齢や運動量に応じてカロリーを的確に調整し、栄養バランスの取れたドッグフードを選ぶことが大切です。
また、間食やおやつを与えすぎることは適正体重を保つ妨げになるため、与える量や頻度の管理が重要です。
過剰なカロリー摂取は肥満だけでなく、糖尿病や関節への負担増加といった健康トラブルの原因にもつながります。適切な食事管理を徹底し、免疫力の維持、肥満や病気の予防を心がけていきましょう。
②十分な運動
ビーグルはもともと猟犬として働いていた歴史があり、十分な運動が欠かせません。
ビーグルの平均的な運動量としては、1日に30分以上の運動を2回程度行うことが理想的です。散歩だけでなく、ボール遊びやジョギングなど変化のある運動を取り入れることで、犬のストレス発散に効果的です。
適度な運動は肥満の予防や心肺機能の向上、そして精神面の安定にも繋がります。
③日々のお手入れ
ビーグルは被毛が密集しており通気性が低く蒸れやすいと言われています。
また、皮脂は平均より多い傾向があり、臭いが気になる場合もありますが、定期的な被毛のお手入れは皮膚の健康維持や臭いの軽減にも効果的です。
また、外耳炎などの耳の病気を防ぐためにも耳掃除を定期的に行いましょう。
常に被毛や皮膚の状態を観察し、普段と違う症状が見られた場合はすぐに動物病院で相談することが大切です。
④定期的な健康診断
シニア期に入ると体力や免疫力が低下しやすくなり、さまざまな病気にかかるリスクが高まります。
定期的な健康診断を受けることで病気を早期に発見し、適切な治療を受けることができるため、健康を維持しやすくなります。
犬の健康寿命を延ばし生活の質を高めるためにも、若い頃から年に一度は獣医師による診察を習慣付けておくことが大切です。
⑤スキンシップ
日々のスキンシップは愛犬の体調を把握するだけでなく、精神的な安定にもつながります。
スキンシップによりストレスが軽減し、愛犬との信頼関係が深まることで精神的な満足感が生まれます。これが免疫力の向上にも好影響を与えると考えられています。
心身の健康維持に欠かせないコミュニケーションとして、日常生活の一部に積極的にスキンシップを取り入れることが、健康寿命を延ばすポイントの一つです。
シニア期に入った際の注意点
シニア期に入ると体力や免疫力が徐々に低下し、さまざまな健康トラブルが起こりやすくなります。
食事に関しては、年齢に合った量や栄養バランスの整ったフードを与えましょう。消化に良いものを選ぶのもポイントです。
また、無理のない範囲での運動習慣を維持することで健康を維持できます。年齢が進むにつれて関節や筋肉の衰えが目立つため、動き方や身体の触れ方に注意し、普段と違う歩き方や痛みのサインがあれば早めに動物病院に相談しましょう。
定期的な健康診断を受けることで病気の早期発見につながり、犬の平均的な健康寿命を意識した適切なケアや治療が可能になります。
シニア犬はストレスにも敏感になりやすいので、静かで安心できる環境を整え、十分な休息を取らせることも大切です。
まとめ
大切な愛犬といつまでも元気で暮らしていくためには、愛情をもって日々の健康管理を続けることがポイントとなります。
絆をさらに深めるためにも、犬の個性や健康状態に合わせたケアを心がけ、豊かで穏やかな毎日を目指しましょう。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、少額短期保険募集人の資格を保有。
豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら