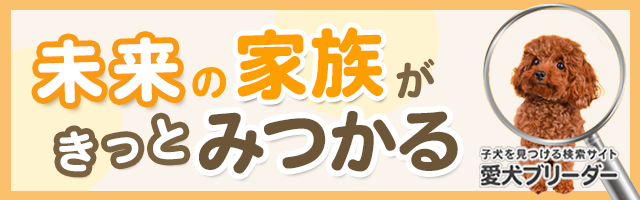室内犬として飼いやすい犬種ランキング!特徴や飼育方法などもご紹介
公開日:2025年4月15日
更新日:2025年5月23日

近年では「犬は家族」という考え方が広まり、多くの人々が犬を室内で飼育するようになっています。
特に初心者の方にとっては、どの犬種が室内で飼いやすいのか、またどのような準備が必要なのかといった点が気になることでしょう。
これから室内で犬を飼育したいと考えている方に向けて、おすすめの犬種や飼育方法など詳しくご紹介します。
室内で飼いやすい犬を選ぶポイント

犬を迎える際には、いくつかのポイントを考慮することが重要です。
今回は室内で飼いやすい犬を選ぶポイントを6点ご紹介します。
ポイント①抜け毛が少ない
抜け毛の少なさや毛が抜けない特性を持つ犬種は非常に重要なポイントとなります。
特にアレルギーを持つ方にとって、抜け毛や毛が抜けない犬種を選ぶことで健康面でのリスクを減らすことが可能です。また、抜け毛が少ない犬種を選ぶことで日々の掃除の負担を軽減でき、室内の清潔感を保つのも容易になります。
毛が抜けない犬種は犬自身のケアも簡単であり、飼い主と犬双方にとって快適さを向上させる要因となります。
ポイント②吠えにくい
マンションやアパートなどの集合住宅では、吠えないまたは吠えにくい犬種を選ぶことが求められます。
犬が頻繁に吠えることは近隣住民とのトラブルの原因となり得るため、静かに過ごせる環境を整えることが重要です。吠えない傾向がある犬種は周囲との調和を保ちやすく、飼い主との信頼関係も築きやすいとされています。
犬の性格や性質に関わらず無駄吠えを控えるための適切なしつけを行うことで、より良い共生環境を実現することが可能です。
ポイント③性格が穏やか
室内犬として飼いやすい犬種は、穏やかな性格を持つことが多く、多くの家庭に適しています。特に小さな子供がいる世帯では、性格が穏やかな犬は安心して飼いやすい選択肢と言えます。
性格が穏やかな犬は、家庭内での共存をスムーズにするだけでなく、他の家族との良好なコミュニケーションを築く助けとなります。
また、防衛本能が比較的弱い傾向があるため突発的な来客や初めて会う人にもフレンドリーな対応をしやすく、家庭全体の安心感を得られるのが特徴です。
ポイント④体の大きさ
体の大きさは、室内犬を選ぶ際に非常に重要なポイントです。
狭いスペースで飼育する場合、小型犬や中型犬が適していることが多いです。小型犬は、そのコンパクトな体の大きさから扱いやすく、限られた生活空間にもすんなりと馴染むことができます。
また、中型犬も適度な運動と環境が整えば、室内飼いに適した種類が多く存在します。
一方で、大型の犬種は広い室内や運動できるスペースが必要となり、狭い環境ではストレスを感じることがあるため注意が必要です。
ポイント⑤しつけがしやすい
しつけのしやすさは、犬種選びの際に重要な側面です。
犬が室内で生活するには、トイレのしつけ、無駄吠えの対応などが欠かせません。しっかりとしたしつけが行いやすい犬種を選ぶことで、飼い主と犬との間で良好な関係を築くことが可能です。
しつけが簡単な犬は、初心者の方にとっても安心感があります。
ポイント⑥運動量が少ない
運動量が比較的少ない犬は、室内で飼いやすい犬として注目されています。
多くの運動量を必要とする犬は、狭い空間ではストレスを感じやすく、それが問題行動に繋がる可能性もあります。運動量が少ない犬種を選ぶことで、適応しやすく室内でも快適な環境を提供することができます。
こうした犬種は、仕事や家庭の予定で散歩の時間を十分に確保することが難しい場合でも負担を軽減できるため、忙しいライフスタイルにも適応しやすいという利点があります。
飼いやすい犬種ランキング
飼いやすい犬種は、その特性や魅力によりさまざまな家庭で親しまれています。
中でも、おすすめの犬種をランキング形式で詳しくご紹介します。
【1位】トイプードル

トイプードルは、特に初心者に優しい犬種として知られています。
賢く学習能力が高いため、しつけがしやすい特徴があります。また、毛が抜けない犬種としても広く知られており、抜け毛の掃除が気になる方やアレルギーを持つ方にも適した犬種です。
性格は穏やかで愛情深く、他の犬や人とも上手に交流できるため、家庭の一員として理想的です。
毛が抜けにくい分、定期的なブラッシングやお手入れは必要ですが、その手間以上に飼い主の生活に豊かさや喜びをもたらしてくれる存在です。
【2位】チワワ

チワワは世界最小の犬種として知られる小型犬で、小さな体ながらも非常に勇敢な性格を持っています。
愛情深く、特に飼い主に対する忠誠心が強いことが特徴です。また、おもちゃで遊ぶことが大好きで、活発に動き回る姿が愛らしく、家庭に賑やかさをもたらします。
一方で、警戒心が強く、防衛本能が発達しているため、しっかりとしたしつけを行うことが重要です。これにより、無駄吠えを防ぎ、ストレスのない快適な生活を送ることができます。
適切なケアと愛情をもって接することで、特有の個性をより引き出すことができるでしょう。
【3位】ミニチュアダックスフンド

ミニチュアダックスフンドは、胴が長く短い足が特徴で、歩く姿がとても可愛らしいと人気の犬種です。
性格は陽気で好奇心旺盛であり、家庭内で楽しく過ごすことができます。もともと狩猟犬として活躍していたことから、活発で適度な運動が必要です。
また、小型犬でありながら吠え声が大きいこともあり、無駄吠えを防ぐためのしつけを早い段階から進めると良いでしょう。
室内でも元気に遊べる性格ですが、体格的にヘルニアになりやすい一面があるため、散歩や日々の体重管理をしっかり行うことが健康維持のために重要です。
【4位】ポメラニアン

ポメラニアンは、小さくても存在感のある愛らしい犬種で、多くの人々に愛されています。その特徴的なフワフワとした豊かな被毛は見た目の魅力を引き立て、多くの飼い主を魅了しています。
ポメラニアンの性格は非常にフレンドリーで、遊び好きな一面があり、家族との時間を大切にします。さらに、飼い主に対して高い忠誠心を持ち、愛情深い行動で絆を深めます。
性格上、しつけが十分でない場合には無駄吠えが増える可能性があります。そのため、適切にしつけを行うことが重要です。
ポメラニアンはその可愛らしい外見だけでなく、明るい性格や適応力の高さからも、多くの人々に理想的な家庭犬として選ばれています。
【5位】マルチーズ

マルチーズは、純白で美しい被毛を持つ小型犬です。
その被毛は非常に細く絡まりやすいため、日々のブラッシングが欠かせません。また、被毛が常に伸び続ける特徴があるため、見た目を整えるだけでなく健康を保つためにも定期的にドッグサロンでトリミングを行いましょう。
性格は温厚で素直なため、しつけがしやすく、子供がいる家庭でも安心して飼うことができます。
さらに、運動量が比較的少なく自宅の中でもストレスを感じにくいことから、室内犬として理想的な犬種と言えるでしょう。
【6位】フレンチブルドッグ

フレンチブルドッグは、特有の顔立ちと愛くるしい性格が魅力の犬種で、多くの人に「飼いやすい犬種」として知られています。
おとなしい性格で無駄吠えが少ないため、集合住宅での飼育にも適しています。
運動量がそれほど多くないため、毎日の散歩も適度で済み、仕事や日常が忙しい方でも無理なくお世話ができます。
ただし、フレンチブルドッグは暑さに弱いという特徴があり、特に夏場の高温多湿な環境では注意が必要です。エアコンなどを活用して適切な温度管理を行うことが大切です。
ケアをしっかり行えば、穏やかで人懐っこい性格を発揮し、家庭にとって素敵な仲間となることでしょう。
【7位】ヨークシャーテリア

ヨークシャーテリアは、小型犬としての代表的な存在で、小柄ながら非常に元気な性格が魅力の犬種です。その愛らしい外見と性格から多くの家庭で愛されています。
非常に忠実で飼い主への愛情表現が豊かであるため、しっかりとした信頼関係を築くことが比較的容易ですが、プライドが高い一面を持つため、早い段階から適切なしつけを行うことが重要です。
特徴的な細い毛は抜け毛が少ないため、お手入れがしやすいだけでなく、アレルギーに配慮した飼育が可能です。
運動量は小型犬ならではの控えめなものなので、毎日の散歩の頻度も少なく済む点が忙しい飼い主にとって嬉しい特徴と言えます。
【8位】シーズー

シーズーは、愛らしいルックスと穏やかな性格を持った犬種で、多くの家庭で愛されています。
人懐っこく、他の犬や人ともすぐに打ち解けられる社交的な性格があり、吠えることが少ないため集合住宅でも飼いやすいのが特徴です。
また、運動量は比較的少なめで、日常的な散歩や室内での生活にも適応できます。
その被毛は気高い雰囲気を漂わせ、丁寧な手入れを施すことでさらに魅力を引き立てることができます。
ただし、定期的なケアが欠かせないだけでなく、日本の高温多湿な気候では皮膚にかぶれや炎症を引き起こす場合があるため、空調管理やスキンケアも重要です。
【9位】ミニチュアシュナウザー

ミニチュアシュナウザーは、独特なひげや眉毛が特徴的で、非常に賢く高い知能を持つ犬種です。その知性から、しつけも比較的容易に行えるため、初心者の飼い主にも適しています。
元々使役犬としての歴史を持つことから、勇敢で警戒心が強く、家族を守ろうとする姿勢が見られます。
また、愛情深く従順な一面もあり、適切な環境で愛情を注がれることで、より親密な関係を築くことができます。
運動量は他の小型犬に比べると多めで、日常的に散歩や遊びを取り入れながらしっかり体を動かすことが求められます。無理な運動は避けながら、毎日一定の運動時間を確保し、しっかり体力を使わせるのが理想です。
やや暑さに弱い傾向があるため、特に夏場は室温や湿度の管理に注意し、快適に過ごせる環境を整えてあげることが大切です。
【10位】パグ

パグは、小型犬ならではの魅力を持つ犬種で、しわしわの顔と丸まったしっぽが特徴的です。
性格は明るく、非常に社交的で、人懐っこさが際立ちます。誰にでも友好的に接し、来客にも警戒心を示すことが少ないため、家庭犬として多くの人々に親しまれています。
また、パグはマイペースな一面も持ち合わせており、その特性を理解しながら、オンとオフをうまく切り替えるしつけを行うことが大切です。
運動量は比較的少なくて済むものの、体重が増えやすい傾向があるため、健康管理に注意が必要です。
室内で快適に過ごせるため、集合住宅や都市部の家庭にも適しています。
室内飼育に必要な準備とアイテム
室内で犬を飼う際には、事前にいくつかの準備を行うことが重要です。適切なアイテムを揃えることで、犬との生活が快適でスムーズになるでしょう。
リード
リードは、犬との散歩に欠かせない必需品です。
適切なリードを選ぶためには、まず犬の体重やサイズに合ったものを選ぶことが大切です。
小型犬には軽量で取り扱いやすいリードが適しています。大型犬には、耐久性が高くしっかりとした作りのリードを選ぶと安全です。
リードの長さも選ぶ際の重要なポイントです。短すぎるリードは犬の動きを制限しすぎることがあり、逆に長すぎるリードは人や他の動物との接触事故を引き起こすリスクがあります。
一般的には1.2~1.8メートル程度の長さが、多様な状況で使いやすいとされています。
近年人気の伸縮式リードは、犬に一定の自由を与えられるという利点がありますが、誤った使い方をすると巻き込み事故や制御不能になる可能性もあるため、取り扱いには十分注意が必要です。
人混みや交通量の多い場所では、従来型のリードを使用する方が安全性が高まります。
さらに、リードの素材も選ぶ際に注目すべきポイントです。
ナイロン製は軽くて扱いやすい一方で、強力な犬が引っ張ると摩耗が早まる場合があります。一方で、革製のリードは耐久性が高く、高級感があり長く使用できますが、水濡れや管理がやや難しい点があるので適切なケアが必要です。
このように、リード選びには犬の特性や使う状況に応じた選択が求められます。
トイレ用品
トイレのしつけは、室内犬と飼い主の生活を円滑に進めるために必要不可欠です。
トイレシーツを用意する場合、犬のサイズに合わせた種類を選ぶことが大切です。シーツには吸収力の高いものから、消臭効果が期待できるものまでさまざまなタイプがあります。
加えて、トイレの場所を決めたら毎回同じ場所を使用させることで、習慣化しやすくなります。トイレ用のコンテナやトイレトレーニングのためのサポートアイテムも併用すると、より効果的なしつけが可能です。
ケージ
ケージは、犬にとって安全かつ快適な空間を提供するためのアイテムです。
ケージのサイズは犬の大きさに合ったものを選び、自由に動けるスペースが確保されていることが重要です。内部にはクッションや毛布を敷いて、居心地の良い環境を整えます。犬が落ち着けるよう、明るすぎない場所に配置することが望ましいです。
また、ケージが「居場所」として認識されるように、ポジティブな体験と関連付けさせると安心感を高められます。
安全な室内環境を整える
室内飼育では、安全な環境作りが非常に重要です。
すべての部屋に、犬がアクセスできる場所とできない場所を明確に分けることが必要です。例えば、危険な物や小さな物が散乱している場所は、できるだけ犬が近づかないように配慮することが求められます。
また、電気コードやコンセントの位置にも気を付け、犬が噛んだり引っかかったりしないように保護するアイテムを使うと良いでしょう。
さらに、室内に有毒な植物がないか確認しておくことも大切です。
一人暮らしで犬を飼う際のポイント
一人暮らしで犬を飼う際にも、注意や配慮が必要です。
今回は3つのポイントをご紹介します。
ポイント①犬種の選び方
一人暮らしで犬を飼う際には、特にサイズや性格、必要な運動量を考慮することが大切です。
大型犬は十分なスペースや運動環境の確保が難しい場合があるため、小型犬を選ぶことで、お互いにストレスの少ない生活を送ることができます。
小型犬は一般的に扱いやすく、散歩や日常のケアにおいても負担が軽減されることが多いです。また、性格が穏やかで初心者でも飼いやすい犬種を選ぶことで、日常生活がより快適になります。
さらに、しつけがしやすい犬種を選ぶことも重要です。
特に一人暮らしの場合、トイレのしつけがスムーズに進む犬種であると、時間的な負担を軽減でき、飼い主の安心感にもつながります。
迎えようとする犬種が自分のライフスタイルに合っているかどうかを事前にしっかり調べておくこともおすすめです。
ポイント②留守番中の環境づくり
留守番の環境を整えることは、一人暮らしで犬を飼う際に非常に重要です。
飼い主が不在の間、愛犬が安全で快適に過ごせる空間を確保することが求められます。
飼い主がいない間に起こるトラブルやいたずらを防ぐため、サークルやケージでのお留守番をおすすめします。日頃からこれらに慣れさせておくことで、犬はストレスを感じることなく安心して留守番ができるようになります。
犬がリラックスできるように普段から使っているクッションやおもちゃを配置してあげるのも良いでしょう。また、いつでも愛犬の様子が見られるよう、ペットカメラなどのツールも活用してみてはいかがでしょうか。
日常的に十分なスキンシップを取るなど、普段から信頼関係を築くことで留守番中の不安を軽減させ、犬との生活をより快適なものに近付けていきましょう。
ポイント③コミュニケーションの時間確保
犬との良好な関係を築くためには、定期的なコミュニケーションの時間を確保することが欠かせません。
一人暮らしで忙しい場合でも、犬とのスキンシップを意識的に取り入れることが大切です。特に散歩の時間は、単に運動の場としてだけでなく、犬との信頼関係を深める貴重な機会となります。
また、遊びやお手入れの時間を取り入れることで、犬の性格やニーズを理解する助けとなり、相互理解が進みます。
一人暮らしで時間が限られている方も、少しでも毎日犬に寄り添うことで、不安を軽減し、安心感を与えることが可能です。
抜け毛対策とお手入れ

犬を飼う際には、抜け毛対策やお手入れがとても重要です。
特に室内で犬を飼う場合、床や家具に付着する抜け毛が気になる方も多いでしょう。この問題を軽減するためには、日々のケアを怠らないことが求められます。
定期的なブラッシング
ブラッシングは、犬の毛の健康を保つために欠かせないケアです。
特に長毛種やダブルコートの犬は、毛が絡まりやすく放置すると毛玉ができやすいため、定期的なブラッシングが求められます。
また、ブラッシングにより毛艶が良くなり、犬の見た目が美しくなるだけでなく、皮膚の血行を促進する効果もあります。その結果、皮膚トラブルの予防や早期発見にも役立ちます。
最低でも週に一度はブラッシングを行い、毛の状態を確認する習慣をつけましょう。
犬が嫌がる場合には、遊び感覚でリラックスさせながら行うことで、日常のケアをストレスなく続けることができます。
シャンプー
犬のシャンプー頻度は、犬種や生活環境によって異なります。
一般的には月に1回から2回のシャンプーが推奨される一方で、活発に動き回る犬や外で遊ぶことが多い犬は、汚れが付きやすいため、より頻繁にシャンプーが必要になる場合もあります。
シャンプー選びは皮膚の健康を守る上でとても重要で、特に犬専用の低刺激性のものを使用することで、肌への負担を軽減しつつ毛が抜けないケアにもつながります。シャンプー後にはしっかりと洗い流し、洗剤の残留物を防ぐことも大切です。洗い残しがあると皮膚トラブルの原因となりかねません。
シャンプー後は毛を丁寧に乾かしましょう。湿気によるトラブルを予防し、犬の健康な被毛と皮膚を維持する一助になります。
部屋の清潔を保つ方法
犬を室内で飼う場合、部屋の清潔さを保つことは飼い主の重要な責任です。
抜け毛や犬の匂いを防ぐためには、こまめな掃除が欠かせません。掃除機をかけたり、ウェットシートで拭き掃除を実施することで、毛や汚れを取り除きやすくなります。
また、犬が使うベッドやクッションなどの洗濯も定期的に行うことで、衛生的な環境が維持されます。さらには、空気清浄機を使用することで、室内の空気を清潔に保つことができる効果的な方法です。
室内犬としてのしつけのコツ
室内犬を飼う際には、しつけが非常に重要です。初めて犬を飼う場合は、しっかりとしたしつけによって犬との快適な生活を築くことができます。
ここでは効果的なしつけのポイントを3つ紹介します。
トイレのしつけ
トイレのしつけは、犬との生活において最も重要な課題の一つです。
特に室内犬の場合、失敗が部屋の清潔さに直結するため、早い段階で明確なルールを設けることが求められます。
まず、決まった場所にトイレシーツを敷き、その周辺で犬が用を足すように誘導します。食後や寝起きのタイミングなど、特定のアクションを行った後はトイレに連れて行くことで、犬がトイレの習慣を理解しやすくなります。
また、成功した際には褒めることを忘れずに行い、ポジティブな強化を促進すると良い結果が得られます。
無駄吠えへの対応策
無駄吠えが多い犬に対しては、適切な対応策を講じることが重要です。
犬が吠える理由は様々で、不安、退屈、要求、外部環境からの刺激が主な原因となることが多く見られます。まずは愛犬がなぜ吠えているのか、その原因をしっかりと見極めることが求められます。
例えば、他の動物や通りを行き交う人々の動きに反応している場合もあるため、犬がそのような刺激を受けて吠えたときには、無視することで反応を和らげさせる方法が有効です。このアプローチにより、犬に「吠えても効果がない」ということを理解させることができます。
加えて、注意を引くために吠えた場合にも無視を徹底しましょう。また、静かにしている時間を褒めたりご褒美を与えたりすることで、「吠えない」状態をポジティブに強化することができます。
散歩や遊びなどを通して十分な運動や刺激を日常的に与えることも無駄吠えを防ぐうえで非常に効果的です。適度な運動は犬のストレスを軽減し、エネルギーを発散させるため、無駄吠えの頻度を大幅に減らす助けになるでしょう。
噛み癖を防ぐには
犬が噛む行動は、しつけの中でも特に対処が必要な問題の一つです。
犬が噛む理由には、遊びの延長や緊張、ストレスが含まれます。
噛み癖を防ぐためには、まずは適切なおもちゃを用意し、噛むことが許可されているものを明確にすることが大切です。そうすることで、犬は与えられたおもちゃに集中し、間違って人を噛むことを避けられるようになります。
また、噛むことに興奮した際には、すぐに「NO」と言って静かにさせる必要があります。
しつけを行う際には、一貫性が重要であるため、全ての家族メンバーが同じルールを遵守することも大切です。
まとめ

(ハクちゃん・トイプードル・9歳)
犬は飼い主にとって大切な家族の一員となる存在です。
犬との生活は大変なこともあるかもしれませんが、得られる喜びや癒しはそれを上回る魅力があります。
室内で飼いやすい犬種との暮らしは、忙しい現代人の生活に心の豊かさをもたらしてくれるでしょう。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、犬のしつけインストラクター、少額短期保険募集人の資格を保有。豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。
運営会社はこちら
犬種の関連記事
犬種の記事一覧を見る人気の記事
新着記事